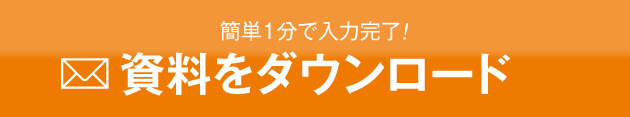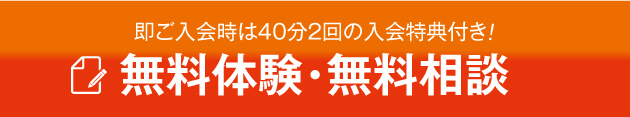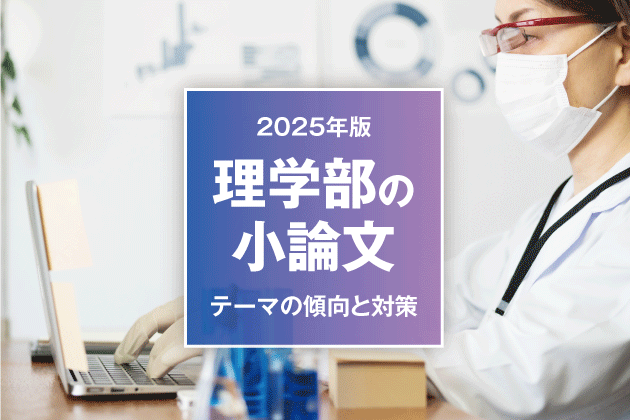指定校推薦は憧れの志望大学を有利に受験できるチャンスです。自分でも利用できるのか気になっている方もいるのではないでしょうか。今回は、指定校推薦とは何かがわかるように、概要や現状、条件、もらうにはどうすべきか、落ちたときの対応などを解説します。指定校推薦の利用を検討している方はぜひ参考にしてみてください。
目次
指定校推薦とは?
指定校推薦は一般受験とは入試の仕組みが大きく異なり、制度を正しく理解しなければ適切な対策を打てません。まずは指定校推薦入試の全体像がわかるように、概要や現状、条件、決め方などを解説します。
概要
指定校推薦とは、学校推薦型選抜入試の一種であり、大学が指定した高校の生徒だけが出願できる推薦入試制度です。
たとえば、さいたま市立浦和南高等学校は、東京理科大学や武蔵大学、大妻女子大学などさまざまな大学の指定校となっています。そのほか、新島学園は関西の難関私立大学である同志社大学について37名の指定校推薦枠を確保しています。
基本的には大学が高校の進学実績をもとに指定するのが一般的です。通学している高校が指定されていなければ成績が良くても出願できません。
参照:
学校推薦型選抜入試の概要、同志社大学の概要を知りたい方は下記の記事を参考にしてみてください。
学校推薦型選抜入試とは?種類や対策、受かる人、落ちる確率などを解説!
関関同立とは!各大学の偏差値や特徴、就職先、著名な卒業生について紹介!
現状
推薦入試の枠と合格者数は増加傾向にあり、今後も同様の流れが続く可能性が想定されます。
ただ、学習態度が良好であれば簡単に出願できる傾向も強まり、目的意識や基礎学力が低い指定校推薦の合格者も珍しくなくなりました。
退学の問題も浮き彫りになっており、大学側としては志だけでなく学力も高い学生を厳格に選抜する必要に迫られています。したがって、偏差値の高い高校への指定校推薦枠が増え、偏差値が低い高校の枠は減る可能性も危惧されます。
近年は学校推薦型選抜入試に基礎学力テストを導入する大学も増えてきました。引き続き、推薦入試でも学力が重視される風潮が広まっていくかもしれません。
基礎学力テストの導入事例について詳細を知りたい方は下記の記事をご覧ください。
学校推薦型入試に学力は重要? 基礎学力テストの導入事例、対策を解説!
条件・決め方
指定校推薦では基本的に条件は明記されず、高校別に評定の条件が設けられていることが多いです。
推薦を獲得するには高校の内部選考で勝ち抜く必要があり、評定をはじめとする学習成績に関する数値が決め方の基準となります。
ただ、評定が同じ場合も発生するため、課外活動や部活動、取得資格、高校生活の取り組みなども総合的に評価されるのが一般的です。
なお、合格したときの入学を確約することも前提条件とされる場合があります。
指定校推薦をもらうには?
指定校推薦をもらうにはライバルよりも早く対策をすることが最も重要です。限られた枠を獲得するための具体的な対策を解説します。
指定校推薦枠の有無を確認する
指定校推薦の枠については、高校が積極的に情報を発信しないことが多い傾向です。そのため、基本的に興味のある生徒が自ら指定校推薦の概要、推薦枠について教師に確認しなければなりません。確認したとしても、明言を避けられるケースも多くあります。
そういったことからも、高校のホームページで確認できないことも多いですが、学校によっては指定校推薦で目指せる大学名を進学実績として掲載していることもあるので、見落とさずに確認してみましょう。入学前の段階であれば学校説明会で確認してみても良いかもしれません。
評定平均を可能な限り高める
高校で設定された評定の条件に達していなければ、指定校推薦を受けることはできません。また、ライバルよりも低い評定だと推薦枠を奪われる可能性も高まります。
したがって、高校3年間の学習成績を数値であらわした評定平均を可能な限り高めることが重要です。高校1年生から模範の態度で授業に取り組み、定期テストや単元テスト、課題テストなどで好成績を獲得していきましょう。
偏差値の高い大学の場合は相応の評定が必要になるため、塾を利用するなどライバルと差をつける対策も必要です。
定期テストや単元テスト、課題テストの対策については下記の記事を参考にしてみてください。
定期テストに役立つ暗記方法は? 科目別の勉強法やいつから始めるべきか解説!
単元テストとは? メリット・デメリット、定期テストとの違い、勉強法などを解説!
課題テストとは? 対策すべき理由や勉強法、結果がやばいときにすることを解説!
教師から評価される実績を増やす
ライバルと評定が同じになったときに備えて、教師から評価してもらえる実績を増やしておく必要もあります。
教師から評価されやすい実績の例は下記の通りです。
・部活動でチームの主力として活躍して全国大会出場を果たした
・生徒会のメンバーとして文化祭や体育祭などの行事を成功させた
・被災地でボランティア活動をしている姿がメディアで紹介された
・高校生では取得が難しい数検や英検の上級レベルに合格した
大学が求める学生像まで意識して実績を獲得しておけば、指定校推薦で合格できる可能性は飛躍的に高まるでしょう。
英検や数検について詳しく知りたい方は下記の記事もご覧ください。
英検は大学受験に使えない? 受験するメリットや共通テストで利用できる大学例を紹介!
英検®の塾は利用すべき?学校で受ける??専門塾と一般塾の違いも解説!
数検とは?レベル・難易度やメリット、優遇される高校・大学の例、対策などを紹介!
入学意志の強さが伝わる志望理由書を書く
校内選考のための申込書内の志望理由記入欄や、校内選考を勝ち抜いた後、指定校推薦をもらうための志望理由書を書くには、入学意志の強さが伝わる志望理由を書くことも大切です。
自分こそが大学を志望するのに相応しいことが伝わるように、大学で学びたいことや、学業を社会で活かすまでのキャリアプラン、大学が求める学生像に合致している根拠などを書きます。
作成方法に不安がある場合、一般的には学校の先生に添削してもらうことになりますが、ほかの生徒もお願いする可能性があるため、ライバルと差をつける仕上がりを目指すことは難しいでしょう。
できれば外部の教育機関で、指定校推薦の対策に詳しい教育の専門家を探して、添削をお願いするのが望ましいです。
Axisのオンライン家庭教師では、指定校推薦の対策に詳しい教育の専門家を全国から探して、自宅で映像通話による添削を受けられます。評定アップのための教科学習もサポートしてもらえるので、指定校推薦に向けた対策を一気通貫で実施することも可能です。
志望理由書の書き方については下記の記事も参考にしてみてください。
総合型選抜・学校推薦型選抜入試の志望理由書の書き方を徹底解説!【例文あり】
指定校推薦で第一志望大学の校内選考に落ちたら?
指定校推薦に向けて対策を行っても、自分よりも推薦されるに相応しい人物がいれば、校内選考に落ちるかもしれません。
ですが、指定校推薦で第一志望の大学の校内選考に落ちたからといって、大学受験に失敗するわけではありません。気持ちを素早く切り替えて最善の進路を目指すことが重要です。
指定校推薦の校内選考に落ちたら検討すべき選択肢を解説します。
別の大学の指定校推薦を検討する
誰からも希望されずに指定校の枠が余ることもあり、2次募集で別の指定校の受験者が募集されることもあります。
高校としては指定校の枠が余ってしまうと、翌年から指定を解除されるリスクが高まるため、教員から勧められることもあるようです。
ただ、希望のキャリアにつながらない大学であれば、進学してから後悔するかもしれません。本当に通いたいと思える大学かどうか熟考して受験を判断しましょう。
※学校によっては初めから第2志望までエントリーするケースもあります。その場合、第1志望に落ちて第2志望に受かったときは必ず受験しなければなりません。
同じ大学の別学科の指定校推薦を検討する
第一志望の校内選考に落ちてしまった場合でも、同じ大学の別学科が2次募集されることもあります。
第一志望の大学でも、1次募集よりもライバルが減るため、校内選考を通過できる可能性が高まります。
第一志望の学科でなくても、学べる学問や打ち込める研究に強く惹かれたり、自分の強みを伸ばせるゼミがあったりするようであれば、選考に臨んでみるとよいでしょう。
大学のゼミについて詳しく知りたい方は下記の記事が参考になります。
大学のゼミとは?何する??意味や講義との違い、高校生が知っておくべき理由も解説!
別の入試方法に切り替える
指定校推薦ではなく、公募制の学校推薦型選抜入試や一般入試で合格を目指すことも可能です。公募制でも評定や資格などをそのまま活かせる場合もありますし、一般入試については学力に自信がある方であれば有利に受験できます。
ただし、公募制に関しても基本的に高校の校長からの推薦が必要です。
出願のトラブルを回避するためにも、校内選考に落ちた場合の公募推薦受験の可否についても念のため事前に確認しておきましょう。
まとめ
指定校推薦はごく一部の優秀な生徒しか受からないと思うかもしれませんが、早くから対策すればライバルを押しのけて合格を勝ち取ることも不可能ではありません。
利用する場合は、高校1年生のときから学校の成績を可能な限り高めて、大学が求める学生像を目指しながら、アピールできる実績を積み上げていきましょう。
高校では学ぶ内容が高度になり、中学よりも好成績を維持するのが難しくなります。
指定校推薦に向けて成績上位者を目指すための対策を始めたい方、指定校推薦についてさらに詳しく知りたい方は弊社ホームページにて。
指定校推薦の利用を含めて進路の決め方に迷う場合は下記の記事もご覧ください。