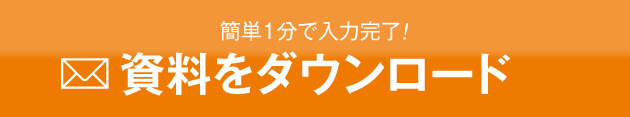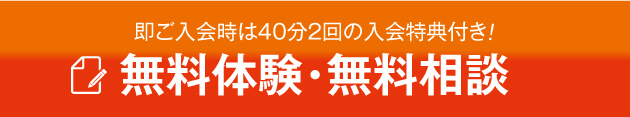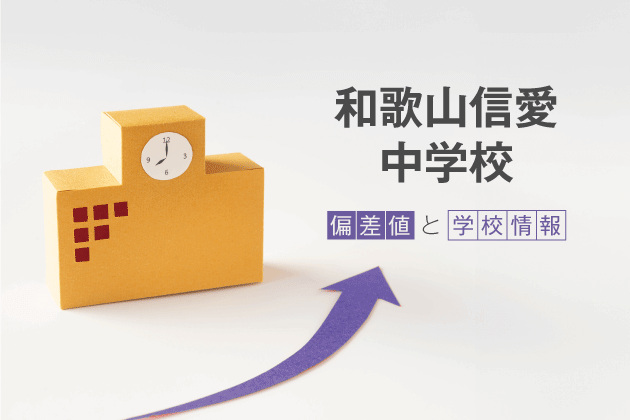大学で身につけた知識をさらに深め、高度な専門性を追求できるのが大学院です。大学学部では基礎的な学問領域を幅広く学びますが、大学院では特定のテーマをより深く掘り下げる研究活動が中心となります。
本記事では、大学院の目的や進学のメリット・デメリット、大学院の種類や入試の流れなど、大学院を検討する上で知っておきたい基本情報をまとめました。進学を考える際の注意点や選び方にも触れますので、将来像を具体的に思い描きながら読み進めてみてください。
自分の研究テーマやキャリアに合った大学院を見つけることは、専門性を高めるだけでなく、社会的ニーズにも貢献できる重要なステップです。より高度な学問の世界を体感し、ライフプランに合った学び方を一緒に検討していきましょう。
目次
大学院の目的・役割とは?
大学院とは、大学を卒業した後にさらに高度な専門知識や研究能力を身につけるための教育機関のことです。
世界的に見ると、19世紀初頭、ベルリン大学(現在のフンボルト大学、1810年創立)が「研究を中心にした大学」モデルを確立しました。その後、アメリカのジョンズ・ホプキンス大学(1876年設立)で初めて設置されたとされ、日本では、1877年(明治10年) 東京大学創設時に「大学院」が設置されました。高度な学術研究の成果を社会や産業界に還元することも大きな使命であり、大学院を通じて育成された人材はリーダーや専門家として活躍する機会も多く得られます。学問の理論を追求するだけでなく、実社会の課題や変化に柔軟に対応できる思考力を培うのも大学院の重要な役割です。
大学院の種類
大学院には複数の形態が存在し、研究内容や学び方が異なります。自分の目的に合った種類を選ぶことが重要です。
大学院と一口に言っても、実はさまざまな制度や構造があります。同じ大学の中に「学部(学士課程)」と「大学院(修士・博士課程)」が両方設置されている形態、つまり学部と併設されている大学院や、独立して運営されている大学院大学、さらには法律やビジネスなど特定の専門領域に特化した専門職大学院など、ニーズに応じて形態は多彩です。目的や研究分野に応じて最適な大学院を選ぶことで、学習効率や将来のキャリアアップにも大きく影響を与えるため、事前によく比較して検討する必要があります。
学部を持つ大学院
学部を持つ大学院は、同じ大学の中に「学部(学士課程)」と「大学院(修士・博士課程)」が両方設置されている形態なので、学部生がそのまま進学しやすい環境が整っているケースが多く、同じ大学の中で学士課程から修士・博士課程まで一貫して用意されているというメリットが得られることがあります。
東京大学では、学部は法学部、大学院は法学政治学研究科という例が挙げられます。
大学入試の時期から将来を見据えて大学院進学を考え、どういった学問を学びたいのかを明確にしておくと、総合型選抜入試の志望理由書にも書きやすく、説得力のあるものになります。
総合型選抜・学校推薦型選抜入試の志望理由書の書き方を徹底解説!【例文あり】
大学院大学
大学院大学は大学院単独で運営されており、研究分野をより特化させていたり、学際的な研究を重視していたりする特色が見られることが多いです。学部教育は行わず、研究者養成や高度専門教育に集中しており、特定分野(情報・国際関係・政策・医療など)に特化して設立されるケースが多いです。それぞれの強みや特色を理解した上で、自身の研究テーマやキャリアに合った形態を選びましょう。
国際大学(IUJ、新潟)、沖縄科学技術大学院大学(OIST、沖縄)、総合研究大学院大学(SOKENDAI、神奈川・葉山)などがあります。
独立研究科
独立研究科は、学部に対応する学部が存在しない大学院研究科のことで、特定の分野に深く焦点を当てたカリキュラムが特徴です。高度な専門研究を中心に据え、共同研究やプロジェクトベースでの学習を行う場合が多く、学際的なテーマに取り組みたい学生にも向いています。学部の枠にとらわれず、より自由度の高い研究環境を求める方にとっては魅力的な選択肢となるでしょう。
東京大学の新領域創成科学研究科や、京都大学の情報学研究科がこれに当てはまります。
専門職大学院
法科大学院や経営大学院などに代表される専門職大学院は、実務との結びつきを重視し、実践力を持つプロフェッショナルを育成することを目標としています。講義やケーススタディだけでなく、インターンシップや実習を通じた実経験を重視するプログラムが多い点が特徴です。高度な資格取得や、特定の分野でのキャリアアップを目指す人にとって、専門職大学院は効率的に知識を身につけられる選択肢となります。
法科大学院(ロースクール)や、経営大学院(MBA)がこれに当てはまります。後述の修士号・博士号という学位ではなく、学位は「専門職学位(MBA・法務博士など)」などとなります。
修士課程と博士課程
大学院は修士課程と博士課程に分かれ、それぞれで学ぶ内容や研究スタンスが異なります。
修士課程は、学部で学んだ基礎を深める段階であり、博士課程はさらに独自の研究を積み重ね、新しい学術的貢献を生み出すことを目指します。修士課程終了後に就職する人も多い一方で、博士課程に進む場合は研究職や高度専門職を志すケースが多いため、進学するかどうかは将来的なキャリアビジョンに大きく関わる選択となります。各過程で必要とされる研究の深さやアプローチが変わるため、目指すゴールに合った進路を慎重に検討することが重要です。
修士課程
修士課程(博士前期課程)は、学士号を持つ人、つまり大学卒業者が進むことができます。修士課程では、学部よりも専門性が高い科目や研究テーマに取り組み、研究手法の基礎を学ぶのが主な目的です。大半の学生はここで研究計画の策定や論文執筆のプロセスを身につけ、学会発表などを通じて研究の成果を外部にアピールする経験を積みます。将来的には、企業の研究開発部門や公的研究機関など、より高度な知識が求められる職種への就職にも結びつきやすいステップです。
通常2年(社会人向けは1年制もあり)の在籍年数になり、取得できる学位は修士号(文学修士、工学修士、教育学修士など)です。
博士課程
博士課程(博士後期課程)では、修士課程よりもさらに踏み込んだオリジナル研究を推進し、新しい学術的な知見を生み出すことが求められます。研究室や指導教員との密接な連携のもと、博士論文を完成させるために長期的な研究計画を立て、実験や検証、データ分析に時間をかけるのが特徴です。学内外の学会や論文発表を通じて幅広い研究者と意見交換を行うことで、研究内容を洗練させながら世界的な視野で活動するチャンスも得やすくなります。
通常3年(医学系は4年、最長5年など例外あり)の在籍年数になり、取得できる学位は博士号(博士(理学)、博士(法学)、博士(工学)など)です。
通学制・通信制の比較
通学制と通信制、それぞれに特徴があり、学び方や時間の融通が異なります。自身のライフスタイルや研究計画に最適な選択をしましょう。
通学制の大学院では、研究室やゼミで教授や仲間との交流がしやすく、対面のディスカッションを通じて研究アイデアを深めやすい環境があります。一方、通信制は場所を問わず学べる利点が大きく、仕事や育児などと並行して研究を進めたい社会人にとって有効な選択肢です。実験設備や共同作業が必要な分野は通学制が適している場合が多い一方で、座学中心の文系や理論分野では通信制でも十分に学ぶことができます。
大学院進学のメリット・デメリット
大学院へ進学することによる利点とリスクを正しく理解しておくことが大切です。
大学院進学は、より専門的な研究環境を得られる反面、学費や時間的な負担も大きくなる可能性があります。高度な知識を武器に就職やキャリアアップを図ることができる一方で、研究の進捗具合が予想よりも長引くことも少なくありません。自分の目標やライフスタイルに合った学習計画を立てることで、リスクを最小化しながら大学院生活を充実させることが重要です。
専門研究に没頭できる(メリット)
大学院には、指導教員や専門家のサポートを受けながら特定の研究テーマに没頭できる環境があります。研究に取り組むうちに、論文執筆や学会発表などを通じて専門外の人ともネットワークを築く機会が増え、自分の知見を広げられる点が大きな魅力です。高度な専門性を身につけることで、学術界だけでなく産業界からも求められる人材へと成長できる可能性が高まります。
就職やキャリアアップへの影響(メリット)
修士号や博士号の取得は、グローバル企業や研究機関などの高度専門職の採用で有利に働く場合が多いです。特に博士号を取得すると、研究職や教育職での道が大きく開かれ、自身の名前を冠した研究成果を社会に広く発信できます。ただし、一般企業への就職時には学歴が評価される一方で、実務経験を求められる場合もあるため、計画的なインターンシップや実践的な活動を併せて検討することが望ましいでしょう。
学費・研究負担(デメリット)
大学院進学には、経済的・時間的な負担など、注意すべき点も存在します。
大学院では学費や生活費だけでなく、研究活動に必要な書籍費や学会参加費、場合によっては実験設備の維持費などもかかる場合があり、経済的負担が大きくなりがちです。さらに、研究や論文執筆に追われることで精神的なストレスも増え、スケジュール管理が難しくなることもあります。これらのリスクを適切に把握し、自分の目標や資金計画と照らし合わせて進学を検討することが重要です。
大学院入試の流れと対策
大学院入試では、研究計画書の作成から各種試験形式への対応まで、しっかりとした準備が必要です。
大学院の入試は、大学ごとや研究科ごとに出題範囲や求められるスキルが異なるため、十分な情報収集が欠かせません。研究計画書や英語などの語学試験、さらに面接や口頭試問の有無など、複数の試験対策を同時に進める必要があります。時間的余裕をもって計画を立て、指導教員や先輩のアドバイスを積極的に取り入れることで、合格への可能性を高められるでしょう。本記事では、一般的な入試の流れを記載します。
研究計画書・出願書類の提出
研究計画書は、入学後に取り組む研究テーマや方法を明確化する重要な書類です。学術的な価値や新規性を含め、先行研究の調査状況と自身のアプローチを整理して記述する必要があります。入試の合否だけでなく、配属される研究室を決める重要資料です。
また、出願に際しては、学部の成績証明書や推薦状が必要になるケースもあるため、必要書類の締め切りや手配は早めに確認しておきましょう。
筆記試験
志望分野の基礎から応用知識を問われる「専門科目」と、英語、TOEFL・TOEIC・IELTSのスコア提出で代替できる場合もある「語学」の筆記試験があることが多いです。理系・国際系ではTOEFL・TOEICが重視される傾向です。志望大学院の出願条件を確認し、対象検定を取得しておくに越したことは無いでしょう。
英検®の塾は利用すべき?学校で受ける??専門塾と一般塾の違いも解説!
帰国子女必見!帰国生入試や海外留学に必要なTOEFL・IELTSとは?英検との違い、スコア換算、対策を徹底解説!
面接
志望理由や研究計画の説明、指導を希望する教員と研究テーマについてディスカッションする面接試験があります。しっかりと練習しておきましょう。
その他入試対策
大学受験のような「偏差値競争」ではなく、研究テーマと教員とのマッチングが重視されます。志望研究室の教授に事前にコンタクトしておくことも非常に重要なようです。募集要項にも、受験前に教授へ連絡を取り、進学の相談をしてください、というような記載がある場合がありますが、記載が無くても、教授に事前にメールなどで相談しておくと良いでしょう。ロースクールやMBAでは、教授連絡よりも 出願資格・職歴・志望理由書 のほうが重要です。
一般入試以外の試験形式
大学院入試には、一般入試以外にも複数の受験形式があります。一般入試では専門科目や語学試験、面接などを総合的に評価されることが多い一方、推薦入試・特別選抜は指導教員や大学の推薦を通じて選抜が行われやすくなります。自分のスケジュールや研究テーマのタイミングに合わせて最適な試験形式を選ぶことが大切です。社会人特別選抜や、留学生特別選抜などもあります。志望校や成績に応じて、自身に合った試験形式を選びましょう。
大学院の学費目安と奨学金について
大学院でかかる費用の目安や、金銭的負担を軽減するための奨学金制度について確認しましょう。
国公立の場合、修士課程では年間数十万円ほどの授業料が一般的で、博士課程も同程度もしくはやや高めです。私立大学院はさらに高額になることが多いため、あらかじめ情報を集めておくことが重要になります。奨学金は日本学生支援機構や大学独自の制度など種類が幅広く、研究成果や成績に応じて給付型や貸与型で支援が受けられる場合があるので、早めに確認して手続きを進めましょう。
おおよその学費は「修士課程2年、博士課程3年」を想定すると、国公立なら5年間で約450万円、私立理系なら700~900万円必要なイメージです。
まとめ
大学院で得られる高度な知識と研究経験は、社会的にも大きな価値をもたらします。学びの先に広がるキャリアを見据え、じっくりと進学を検討しましょう。
大学院とは、学問を深めるだけでなく、自らが知見を創出する喜びを得られる特別な場所でもあります。研究を通じて身につけた問題解決能力や批判的思考は、企業や社会で求められるスキルと直結しているため、学術界以外にも多くのキャリアパスが開けるでしょう。自分の興味や将来ビジョンに合った大学院を選び、その可能性を最大限に活かせるように準備を進めてください。
オンライン家庭教師であれば、勉強につまずいたとき、自宅ですぐ講師と対面してサポートを受けられます。大学院合格を目指すために、オンライン家庭教師を利用したい方はAxisのオンライン家庭教師のホームページをご覧ください。