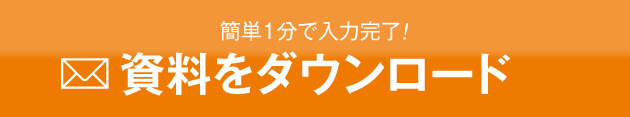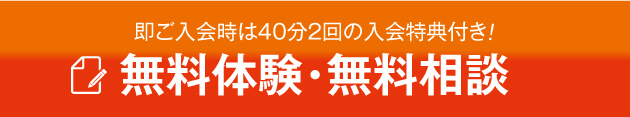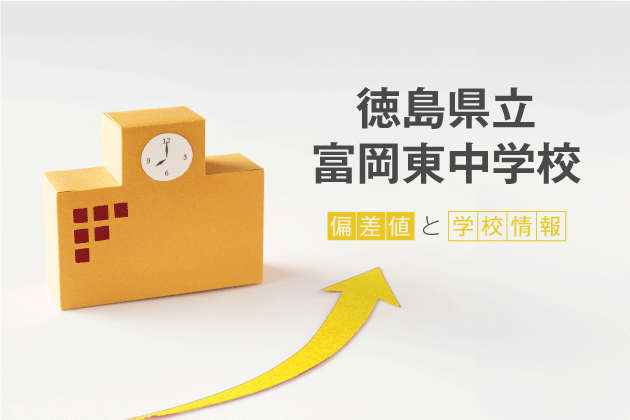受験競争が過熱する現代において、一般受験に関係のない人権作文は中学生・高校生から軽視されがちです。実際は受験においても中学生・高校生が人権作文に取り組むメリットは計り知れず、多くの方が貴重な経験を積む機会を失っています。今回は、早いうちから人権作文に興味を持ってもらえるよう、概要をはじめ構成や書き方、注意点などについて解説します。コンテストに参加する意味にも触れているので、興味を持った方はぜひ挑戦してみてください。
目次
人権作文とは?
人権作文とは人権の大切さや課題をテーマにした文章です。そもそも人権とは、誰もが共通して人として生きるために有している権利であり、他人から決して侵されてはならない権利でもあります。
しかし、多種多様な価値観を持つ人々で構成される社会において、人権を守ることは容易ではありません。
世の中では、人権を守りながら人々が生きやすい社会を形成するリーダーが求められており、高校はもちろん大学や企業でも人権意識の高い人材が求められる傾向にあります。
そのため、中学生・高校生の段階で人権作文に取り組み人権意識を向上させることで、将来的に受験や就職も成功しやすくなるでしょう。
後述しますが、法務省と全国人権擁護委員連合会による、中学生を対象とした人権作文コンテストも全国各地で開催されています。
人権作文の構成・書き方
コンテストで入賞する人権作文を分析すると、一定の構成に基づき書かれていることがわかってきます。人権作文の構成と書き方について解説します。
書き出し
書き出しは読者に続きを読みたくさせる重要な部分です。
小説や漫画、アニメ、映画を思い浮かべながら、興味を惹く導入を意識しましょう。
例としては、冒頭から唐突に自分の記憶に残る強烈な失敗・後悔に触れたり、重要な会話や場面をいきなり表現したりするなどの手法があります。
また、人権とは関連がないように見える書き出しをすると作品への期待感を高めやすいです。意外性のある書き出しを考えてみてください。
エピソード・体験談
一般的には経験できないエピソード・体験談を書くと、作文のオリジナリティが高まり評価されやすくなります。
たとえば、特別支援学級に在籍していた方がその経験を活かせば、普通学級に在籍している生徒では書けない個性あふれる作文を完成させられます。特に悩みを克服した経験は読者に勇気と希望を与えるため、共感もされやすいです。
調査結果
エピソードや体験談はオリジナリティを出すことができても、主観的な内容になりがちです。説得力を高められずに読者から信頼して読んでもらえないこともあります。
「〇人に〇人が経験するいじめ」といったように、調査結果を可能な限り盛り込むことで、作文の信憑性を高めることが可能です。
読者から「本当に?」と思われそうな部分については、数字で根拠を示せないか情報をリサーチしてみましょう。
気づきや考察
エピソードや体験談は自分の気づきや考察を加えることで、人権に関する有益な考え方、価値観を読者にもたらします。
家族や友人などに障害を持つ方がいるのであれば、日常生活で困っていることを目の当たりにしやすいです。
その経験から、多目的トイレや点字ブロックなど、本当に社会のバリアフリーが機能しているかに対する見解を述べることで、障害者が住みやすい暮らしを考えるきっかけを提示できます。
未来への提言、誓い
人権作文の最後は未来への提言、誓いで締めるのが一般的です。読み手に社会課題を解決する当事者であることを意識させ、これからの態度や姿勢、行動を変革させる内容を記載します。
自分自身の強い誓いを掲げることで、読み手を感動させて決意を促すことも可能です。「~であることを忘れないでください」「~ついて考えてほしいです」「~のようになりたいと強く思う」など、読み手を巻き込むような表現を取り入れてみましょう。目標や実践策まで明確に語れると読み手も行動に移しやすくなるはずです。
人権作文の書き方の注意点
人権作文はちょっとした書き方の注意点を把握しておくだけでもクオリティの高い仕上がりになります。ここでは人権作文の書き方の注意点を解説します。
一般論の羅列を避ける
人権作文の書き方の注意点としては一般論の羅列を避けることです。たとえば「人権は大切」「いじめは絶対になくすべき」といったフレーズはありきたりで、読み手が興味を失いやすくなります。
いずれの主張も、体験やエピソードを伝えるだけで読後に理解してもらえるため、実のところ直接書く必要はありません。
文末表現を単調にしない
作文のルールとしては、文末表現を統一するのが一般的です。ちぐはぐな印象を与えないよう、敬体の場合は「~です」「~ます」に統一し、常体の場合は「~だ」「~である」に統一します。ただ、単調な文末が続くと文章が機械的な表現となってしまい、読み手の心を動かすのが難しいです。
「~決心しました」「~だけに満足していないだろうか」のように、文末表現を工夫して変えるだけで、書き手の気持ちや熱意を伝えたり、問いかけをしたりできます。
全国中学生人権作文コンテストとは?
全国中学生人権作文コンテストとは、家庭生活や学校生活などで得た体験に基づく人権作文を評価する競技イベントです。法務省と全国人権擁護委員連合会が主催しています。
人権問題について考え、人権尊重の大切さや基本的人権への理解を深め、豊かな人権感覚を身につけるきっかけとなります。
手書きやパソコンのいずれの方法でも提出可能です。
学校を通しての応募となり、夏休みの宿題として提示されることもあるようです。目安として期限は9月中旬あたりとされています。
参加する意味
作文のコンテストであることから文章力を養うのにも絶好の機会です。入賞など成果を出すことができれば、高校受験の面接などで自己アピールの材料にもできます。
さらに近年の大学受験の傾向としては、総合型選抜入試や学校推薦入試などを実施する大学が増加しており、学力以外に志望理由書や小論文なども重点的に評価されるようになりました。
人権作文に取り組んだ経験は、志望理由書や小論文を書くときの材料となるだけでなく、品質の高い文章を書くことにもつながります。
人権作文が学校で夏休みの課題として出題された場合は意欲的に取り組みましょう。もし出題されない場合は、全国中学生人権作文コンテストにぜひ参加して、入賞を狙ってみてください。
人権作文のテーマが決まらないときは?
人権作文を書いてみたい、あるいは、コンテストに出場したいと思ったけれど、テーマが決まらないこともあるでしょう。
テーマが決まらないときは、普段の学校生活や家庭での会話、友人とのトラブルを振り返ってみてください。喧嘩やいじめ、介護など、小さな気づきから書きやすいと思えるテーマが浮かぶかもしれません。
新聞やニュースを見ると、人権に関するトレンドのテーマが見つかることもあります。大手新聞社のオンラインサイトは無料で閲覧できる記事も多いので、高校生でも気軽に情報収集できて便利です。
法務省が主催しているコンテストの入賞作品を閲覧して参考にする方法もあります。類似テーマでも自分の体験を活かせば、より評価される作文をかけるかもしれません。そのほか「人権作文 (県名など)」でネット検索をすると、自治体がまとめた人権作文集が見つかることもあります。
さまざまな方法で情報収集をすれば、ほかの人が思いつかないテーマを見つけられる可能性が高まるでしょう。
参照:
人権作文に関するよくあるQ&A
人権作文に挑戦するにあたって疑問点が残っている方もいるでしょう。人権作文に関するよくある質問にQ&A形式で回答します。
Q1.人権作文の体験談がないときは?
A1.人権を侵害された人々に話を聞いてみましょう。
たとえば、戦争を経験した高齢者の方に戦時中の苦しみを聞いて、許可をいただいたうえで作文の題材にさせてもらいます。
自分が体験したことではなくても、人々に戦争による人権侵害の恐ろしさや残酷さを伝え、二度と戦争が起こらない世界の実現を呼びかけることができるでしょう。
世の中には、いじめられて心に深い傷を負った人、見た目で差別を受ける人、障害を理由に不当な扱いを受ける人など、人権侵害に苦しむ方は数えきれないほど存在しています。社会を良くするために体験談を提供してくれる方がいないか探してみてください。
Q2.人権作文は何文字以上が目安?
A2.コンテストによって文字数のルールが指定されます。
たとえば、全国中学生人権作文コンテストでは、400文字詰め原稿用紙5枚以内という指定があり、文字数の上限は実質2,000文字となっています。
5枚を超えた場合は審査の対象にならないとのことです。
最低文字数についてはルールが定められていません。基本的には指定された制限ギリギリまで執筆する方が多いようですが、8割程度で入賞する方も見受けられます。
参照:「第44回全国中学生人権作文コンテスト」実施要領(法務省)
Q3.人権作文はAIで作成してもよい?
A3.人権作文のコンテストでは生成AIの活用が認められないこともあります。
たとえば、全国中学生人権作文コンテストでは、生成AIによって自己の体験や考察に基づくことなく創作した文章は、審査の対象とならないとされています。
生成AIを使えば短時間で人権作文を仕上げることは可能です。しかし、ありきたりな文章を作成する傾向があり、作文のオリジナリティは低下します。
コンテストでは、これまでになかった独自の視点、書き方が評価されやすいです。仮に生成AIで作成した文章が審査の対象になっても、入賞を獲得するのは現実的に難しいでしょう。
参照:「第44回全国中学生人権作文コンテスト」実施要領(法務省)
まとめ
大学や企業では、社会を良くする課題解決力や周囲の人々を巻き込む表現力などが評価される傾向にあります。
人権作文に挑戦して、社会で求められる能力や経験、考え方を培うことで、受験や就職を有利に進められる可能性が高まります。
人権作文コンテストや推薦入試に向けて作文の書き方を学びたい方、人権作文の宿題をサポートしてもらいたい方はAxisのオンライン家庭教師にご相談ください。