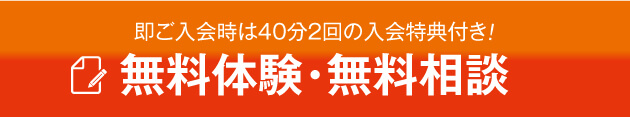これまでの教育現場では、中間テスト・期末テストなどの定期テストが実施されていました。しかし、定期テストの実施には教育上の課題も多く、新たに単元テストが注目されるようになっています。今回は単元テストの概要をはじめ、メリット・デメリット、定期テストとの違い、勉強法などを解説します。単元テストについて理解を深めたい保護者様はぜひ参考にしてみてください。
目次
単元テストとは?
まずは、単元の意味をおさらいしつつ、単元テストの概要や注目される背景について解説します。
単元の意味
単元テストについて知るには単元の意味から理解する必要があります。
単元は特定のテーマに関する学習活動のまとまりです。教師は子どもの興味や教師の願望に基づき単元を創造的に作成します。
評価にあたって、教科ごとに単元指導計画表を作り、教師間で共有するのが一般的です。
なお、単元計画は子どもの状況に応じて作成する必要があり、学校で計画された単元が毎年同じになるとは限りません。
単元テストの概要
単元テストは、単元ごとの理解度や知識の定着度を確かめるためのテストです。
単元を中心とした問題が出題されるので、テスト範囲は狭くなります。
実施方法は学校によって違い、5教科を同時に行う場合や、教科ごとに実施することもあります。
学校は、各出版社が提供している単元プリントを活用したり、事業者のシステムでテストを作成したりすることも可能です。
テストの実施後に補習をして理解度が低い生徒をフォローする学校もあります。
単元テストが注目される背景
これまでの定期テストは、中間テスト・期末テストなどが実施されてきました。
中間テストや定期テストはいずれも成績評価に直結します。中間テストや期末テストだけ好成績を残せば、通知表の評価が高まる場合も多かったでしょう。
そのため、中間テストや期末テストの前に一夜漬けをしてテストに備える生徒も珍しくありません。
ただ、一夜漬けで詰め込んでテストの得点を高めても、知識は定着せずに学習効果が下がる恐れもあります。
なので、定期テストを廃止し、代わりに単元テストの導入を進める学校が増えてきています。
単元テストのメリット
単元テストには定期テストとは違ったさまざまなメリットがあります。単元テストのメリットを解説します。
メリット1.テスト勉強をしやすい
定期テストのように範囲が広いと、学習計画を立てるのが苦手な方は、何から勉強すべきか迷ってしまいます。
その点、単元テストは出題範囲が狭くなるため、勉強すべき内容がはっきりしやすいです。
混乱せずにテスト勉強しやすくなるので、保護者の方が学習計画を細かく作る必要性も減るでしょう。
メリット2.勉強の習慣が定着しやすい
単元テストを実施する学校では、定期テストと違って細かい周期で学習期間が訪れます。
テストとテストの間隔が長期化しないので、テスト後も次回のテストを意識して勉強を継続しなければなりません。途中で学習が途切れにくくなることから、やる気の低下を防ぎやすいです。
定期テストと違って勉強の習慣をつけやすいでしょう。
メリット3.弱点に気づきやすい
定期テストは出題範囲が広くなり、各テーマごとの問題数は少なくなるため、弱点に気づきづらいです。
仮に特定のテーマで正答率が高かったとしても、たまたま出題の相性がよくて正解できている可能性もあります。
その点をふまえると、テーマに特化してたくさん問題を出題できる単元テストのほうが、弱点を正確に把握できます。
単元テストのデメリット
単元テストにはメリットだけでなくデメリットもあります。引き続き、単元テストのデメリットを解説します。
デメリット1.教科・科目以外の教育に影響が出るかもしれない
単元テストを導入した結果、テストの回数が増えてしまうことがあります。
頻度の増加により教員の負担が増えるという見方がありますが、常にテストを意識しながら生活しなければならない点で、お子様の精神的な負担も大きいといえます。
部活や趣味、創作などの時間に集中しづらくなってしまえば、教科・科目以外の教育に関して妨げとなるでしょう。
デメリット2.入試問題に対応しづらくなる
入試問題は広範囲から出題されます。その点、単元テストの範囲は狭いです。
単元テストだけでは入試問題の練習がしづらくなり、学校の学習だけでは志望校対策が不足する恐れがあります。
今後、学校の定期テストが廃止された場合は、学校外の模擬試験で入試対策をすることが重要です。
単元テストと定期テストの違い
ここまでの説明を元に単元テストと定期テストの違いを表にまとめてみます。
| 単元テスト | 定期テスト | |
| 学習スタイル | 日常的 | 集中的 |
| 頻度 | 多い | 少ない |
| 範囲 | 狭い | 広い |
| 勉強のしやすさ | しやすい | しにくい |
| 弱点の発見しやすさ | しやすい | しにくい |
| 教科・科目以外の教育への影響 | 大きい | 少ない |
単元テストは単元が終わるごとに実施される一方で、定期テストは複数の単元を対象として実施されます。
実施方法に伴い、学習スタイルや頻度、範囲などに違いが生じるため、学校がどちらを取り入れるかで日頃の学習の仕方が大きく変わるでしょう。
変化に対応できなければ勉強法を誤ってしまい、単元テストでよい成績を残すのが難しくなります。
突然単元テストが導入されることも珍しくないので、いつ導入されても柔軟に対応できるよう、両方の違いを理解しておくことをおすすめします。
単元テストの成績を高める勉強法
単元テストでよい成績を残すためには、定期テストとは異なる勉強法を確立する必要があります。単元テストの成績を高める勉強法を解説します。
授業中の聞き逃しを減らす
単元テストは、学校によってミニテストの形で実施され、授業をしっかり聞いていれば解ける難易度に設定されることもあります。そのため、授業の聞き逃しを減らすことが得点に直結するでしょう。
授業中、わからないところが気になると、聞き逃しが発生しやすくなります。わからないところに固執せず、不明点は授業後に質問しましょう。
授業のノートを優先して学習する
単元テストは範囲が狭くなる分、定期テストよりも単元を深堀りした問題が出題されやすくなります。その点、授業中に触れられた細かい部分がテストに出題される可能性も高いです。
したがって、授業中に記録したノートの情報がテストの得点源になるといっても過言ではありません。
市販の参考書や問題集を解くことも対策になりますが、ノートの内容を優先して復習する習慣をつけたほうがよいでしょう。
出題される教材の内容を完璧に理解する
学校によっては、単元テストに出題される教材が指定されていることがあります。
指定教材を完璧に理解すれば好成績を残しやすくなります。
単元テストが実施されるよりも早い段階で教材の学習を進め、わからない部分を参考書で理解したり、先生に質問をしたりして解決しておくことが重要です。
まとめ
単元テストの導入が進んでいる状況をふまえると、定期テストの点がよければ成績が高まるという考え方は危険です。
制度が突然変わる可能性もあり、まだ導入されていない学校に通う方も油断はできません。
とはいえ、単元テストのルールは学校によってさまざまであり、対策が難しく感じる場合もあるでしょう。必要に応じて教育の専門家に最新動向を教えてもらい、最適な勉強法を提案してもらうことも重要です。
単元テストの傾向や具体的な対策を知りたい方は弊社ホームページにて。