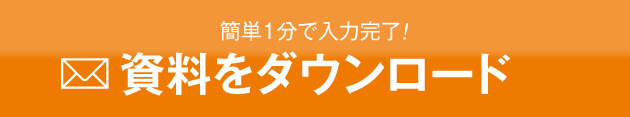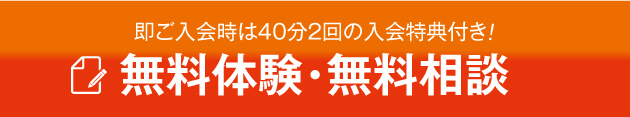内申点は成績を示す数値、受験で評価される数値であることはわかるけれど、具体的にどのような数値なのかわかりづらい指標です。高める方法を理解するためにも、意味をきちんと把握しておきましょう。今回は内申点とは何かがわかるように、意味や通知表・内申書の違い、計算方法、求め方などを解説します。上げ方や裏技についても触れているので、受験を有利に進めたい方はぜひ参考にしてみてください。
目次
内申点とは?
内申点とは、受験において児童生徒の成績、学力を評価するために算出する指標です。内申点の意味を理解するために、まずは通知表・内申書(調査書)の違い、内申点と評定の関係について解説します。
通知表・内申書(調査書)の違い
内申点が記載されるのは通知表・内申書(調査書)のどちらなのか、混乱している方もいるでしょう。そもそも通知表と内申書は別々なのかもわかりにくいかもしれません。
通知表は児童生徒の教科ごとの成績を父母に知らせるための資料です。
その一方で内申書(調査書)は、各教科の成績や学級・生徒会の委員経験、学校行事の活動状況、部活動の実績、出欠日数など、学校生活全般の情報をまとめた資料です。
内申書は通知表と違って父母に向けた資料ではなく、志望校に共有するための資料となっています。
高校受験における合否を判定する際に使われ、一般入試や推薦入試などの出願時に必要とされます。
内申点と評定の関係
評定は、内申書に記載される各教科の5段階評価を示す1~5の数値です。
その一方で、内申点は内申書に記載される評定に基づき計算された成績を示す数値として知られています。
内申点は高校受験の合否判定に用いられるのが一般的です。都道府県の公立学校や私立学校ごとによって判定方法は異なり、学力検査と併用して活用される傾向にあります。
評定と内申点の違いはわかりづらいのか、同じ意味で使われることも多いようです。
高校受験の内申点はいつの成績が評価される?
高校受験の内申点はいつの成績が評価されるのでしょうか。
一般的には調査書に記載されるのは、中学1年生から中学3年生の2学期までの評定が基本です。
ただし、一部の私立高校では推薦入試の出願期間が12月までとなることもあり、中学3年生の1学期までの評定が評価されることもあります。
東京都のように中学3年次の成績のみが評価対象になったり、富山県のように中学1年生の成績は評価の対象外になったりすることもあります。
内申点の計算方法・求め方
内申点は、内申書に記載される評定に基づき計算された成績を示す数値であるとお伝えしました。具体的にどのように計算されるのか気になった方もいるでしょう。
内申点の計算方法、求め方について公立・私立に分けて解説します。
公立
公立高校は都や県、府などによって計算方法、求め方が異なります。
関東の首都圏、関西の主要エリアにおける計算式の例は下記の通りです。
| エリア | 計算方法 | 満点の計算式 | 満点 |
| 東京都 | (中3の5科目の評定合計)+(中3の4科目の評定合計×2) | 5×5+4×5×2 | 65点 |
| 神奈川県 | (中2の9科目の評定合計)+(中3の9科目の評定合計×2) | 9×5+9×5×2 | 135点 |
| 千葉県 | (中1の9科目の評定合計)+(中2の9科目の評定合計)+(中3の9科目の評定合計) | 9×5+9×5+9×5 | 135点 |
| 大阪府 | (中1の9科目の評定合計×2)+(中2の9科目の評定合計×2)+(中3の9科目の評定合計×6) | 9×5×2+9×5×2+9×5×6 | 450点 |
私立
私立の場合も内申点の計算方法、求め方は学校によります。たとえば、9教科の評定をそのまま合計した数値を推薦基準とするパターンがあります。3年次の評定に1がないことを条件とするケースも少なくありません。
そもそも合格条件に内申点が用いられないこともあります。たとえば、面接試験の合格を条件として、学科試験の各教科の合計得点を評価して、合否を判定する高校がよい例です。
必ず受験要項で合否の判定基準に目を通して、内申点の計算方法、求め方が記載されていないか、念のため確認すると安心です。
内申点を上げる対策方法
内申点の計算方法、求め方を知ることで、高校受験における内申点を高める必要性が理解できたのではないでしょうか。ただ、漠然と学業に励むだけでは内申点が高まるとも限りません。
あくまで早いうちから内申点を高めるための対策を講じておくことが大切です。内申点を上げる対策方法を解説します。
定期テスト(中間・期末)などの点数アップ
評定は基本的に学校で行われる中間テストや期末テストなどの定期テストの結果に基づき決まります。
中間テストや期末テスト以外にも、単元テストや課題テストなどが評定に関係する可能性もあります。内申点を高めるには、学校の各種テストに全力で取り組み、基本的に高得点を目指すことが重要です。
定期テストや単元テスト、課題テストの対策については下記の記事もぜひ参考にしてみてください。
定期テストに役立つ暗記方法は? 科目別の勉強法やいつから始めるべきか解説!
単元テストとは? メリット・デメリット、定期テストとの違い、勉強法などを解説!
課題テストとは? 対策すべき理由や勉強法、結果がやばいときにすることを解説!
中学生の定期テストに必要な親のサポート8選! やってはいけないNG行動も理由とともに解説
課題・提出物の徹底
学校の先生はテストだけでなく課題・提出物も成績をつけるときの基準とする場合があります。
課題・提出物をないがしろにする児童生徒は評定が低くなり、内申点まで低くなるリスクが高まります。
とはいえ、たくさんの教科で提出物が発生すると、真面目な児童生徒でも提出日を忘れてしまうかもしれません。手持ちの手帳やアプリのカレンダーなどに提出日をわかりやすく視覚化して、提出漏れの発生を防ぐ仕組みを作りましょう。
授業態度・学習態度・生活態度の改善
テストで高得点を獲得していると、学校で真面目に過ごす必要がないと勘違いして、授業態度・学習態度・生活態度が悪くなることもあります。
授業態度・学習態度・生活態度が悪くても良い評定になれば、ほかの児童生徒が真面目に授業を受けたり規律を守ったりするのが馬鹿らしくなってしまい、学級崩壊のリスクが高まります。
先生の立場としては、授業態度・学習態度・生活態度が悪い児童生徒の評定を下げざるを得ません。内申点を高めるためにも授業を真剣に受けて規則正しく生活しましょう。
内申点は合否判断に影響がある?重要性は??
内申点を高めるためのポイントをお伝えしました。ただ、内申点が合否判断に本当に影響があるのか、まだ疑問を持っている方もいるかもしれません。内申点の重要性について学力検査や推薦入試の観点から解説します。
学力検査と内申点の比率
公立高校の入試では、基本的に内申点が重視されるといわれています。
しかし、難関校ほど学力重視となり、学力検査と内申点の比率が9:1になるケースも想定されます。内申点を重視する学校でも内申点の比重は3割程度になるようです。
内申点で併願校に合格することも不可能ではなく、内申点が高い生徒は受験が有利になることもあります。
推薦入試における内申点の扱い
内申点を推薦入試の出願基準とする高校も見受けられます。設定された数値に届けば一般入試とは異なる受験を認め、数値に届かない場合は一般入試の受験を検討させる仕組みです。
つまり、内申点を高めておけば応募できる入試の幅が広がり、有利に受験しやすくなります。
ただし、内申点の基準を突破したからといって推薦入試に必ず合格できるとも限りません。「推薦入試における3教科の合計得点が4割程度で合格」など、学力を審査されることもあります。
推薦入試を受ける場合は、内申点だけでなく学力を高めておくことも重要です。
内申点以外に一般入試の評価を上げるコツ・裏技
一般入試でライバルと教科の内申点と学力検査の得点の合計が同じであった場合、ほかの基準で合否を判定される可能性も想定されます。ライバルと少しでも差をつけて合格を手にするためには、内申点以外に入試の評価を上げるコツ・裏技を押さえておくことも大切です。
引き続き、内申点以外に入試の評価を上げるコツ・裏技についても解説します。
部活動の実績や生徒会活動の経歴を作る
内申点以外に入試で評価されるためのコツ・裏技として、部活動の実績や生徒会活動の経歴を作る方法が挙げられます。
部活動で都大会や関東大会に出場した実績や、生徒会長として学校行事を取り仕切った実績などがアピール材料となるでしょう。
一般入試では、内申点として得点化されないことがほとんどだといわれていますが、特別活動としての得点枠が用意されることもあるようです。受験する高校で部活動や生徒会活動が評価されるかどうかもチェックしてみましょう。
検定試験(英検・漢検・数検など)に合格する
内申点以外に入試で評価されるためのコツ・裏技として、検定試験に合格する方法が挙げられます。検定の例は英検や漢検、数検などです。
一般入試では、検定試験も部活動や生徒会活動と同様に、特別活動としての得点枠が用意されることもあるようです。
ただ、大幅に内申点を上げることは難しいため、学校の勉強をおろそかにしてまで無理に取得する必要はありません。
内申点アップのために英検や数検を受験すべきか迷う方は下記の記事も参考にしてみてください。
数検とは?レベル・難易度やメリット、優遇される高校・大学の例、対策などを紹介!
英検は大学受験に使えない? 受験するメリットや共通テストで利用できる大学例を紹介!
英検®の塾は利用すべき?学校で受ける??専門塾と一般塾の違いも解説!
ボランティアや地域活動に取り組む
内申点以外に入試で評価されるためのコツ・裏技として、ボランティアや地域活動に取り組む方法が挙げられます。
一般入試では、ボランティアや地域活動の取り組みが、部活動や生徒会活動、検定などと同様に、特別活動として評価される可能性もあります。
入試でほかの受験生と同点で並んだとき、奉仕活動の実績が合否を分けるポイントになるかもしれません。
自ら参加していることや、定期的に取り組んでいること、高齢者・子どもと関わっていることなど、自主性・継続性・社会性をアピールできるように活動しておくとよさそうです。
まとめ
内申点は高校受験の合否に関わる重要な得点です。基本的には、定期テストで高得点を獲得しつつ、模範的な学習態度・授業態度・生活態度で過ごすことで高められます。
ただ、中学の勉強につまずいてしまうと、内申点を上げるのが難しくなります。内申点を下げないためには、規則正しいリズムで学習に取り組むだけでなく、わからないことをスムーズに解消できる環境を整備しておくことが重要です。
オンライン家庭教師であれば、勉強につまずいたとき、自宅ですぐ講師と対面してサポートを受けられます。内申点を高めるためにオンライン家庭教師を利用したい方はAxisのオンライン家庭教師のホームページをご覧ください。