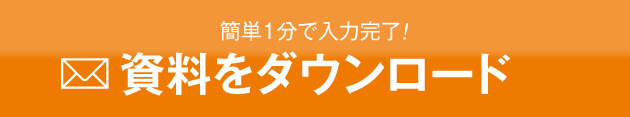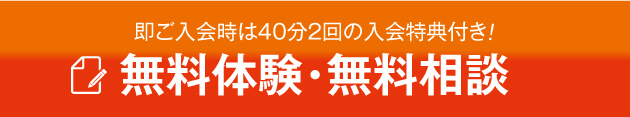大学では高校や中学校などとは違った学びの機会としてゼミがあります。高校生のうちからゼミについて理解しておくことで、大学受験や就職が有利になるかもしれません。今回は大学のゼミは何をするのかわかるように、意味や講義との違い、活動内容の例、高校生が知っておくべき理由などを解説します。進路を考える際にぜひ参考にしてみてください。
目次
大学のゼミとは?何する??
ゼミという言葉はなんとなく聞いたことがあるかもしれませんが、授業や講義と何が違うのか、何をするのかイメージしづらいでしょう。大学のゼミについて理解を深められるように、意味や目的、講義との違い、研究室との違いなどから解説します。
意味・目的
大学のゼミとはゼミナールの略称であり、少人数の学生が教授の指導を受けながら研究・発表・討論をする学習の機会、授業形式です。学部ごとにさまざまな教員が専門分野の研究テーマを掲げて開講します。学生と教授が協力して学問を研究することが目的です。
ゼミナールというと集団塾のイメージがあるかもしれませんが、中学生・高校生が通う塾の場合はどちらかというと、先生から知識や解法などを教えてもらう学習スタイルが一般的です。
大学におけるゼミでは、教えてもらうだけでなく発表や討論の機会もあり、プレゼンテーションやコミュニケーション力、ディスカッション力などを養うことができます。
始まるタイミング
ゼミはいつから始まるのかというと、一般的には3~4年生のタイミングで所属するのが一般的です。1~2年次に論文の書き方を学ぶゼミに参加することもあります。
本格的なゼミに入る前にはエントリーシートやレポート、面接などの選考が行われることもあり、ゼミ選びは大学生活における一大イベントともいわれています。人気のゼミだと倍率が高くなり、必ずしも自分の希望通りのゼミに参加できるとは限りません。
早いうちから入りたいゼミを決めて対策をしておくことも重要です。
講義との違い
ゼミと講義の違いは双方向のコミュニケーションをベースとしているかどうかです。
講義は学問や技術などを学生に説明する方式の授業を意味する言葉です。基本的には教員がテキストの内容を説明しながら黒板やホワイトボードなどに解説を書き出し、学生がノートに書き写す形式で行われます。どちらかというと教員から学生に一方的な情報伝達が行われる印象です。
その一方でゼミは少人数で授業が展開されるため、教員と学生が自然に議論をするような形で特定のテーマについて学びを深めます。教員が教えた内容に対して、すぐに学生から質問が行われたり、個人の見解が述べられたりすることもあります。
研究室との違い
大学におけるゼミと研究室の違いは、場所という性質を持つか持たないかです。
ゼミと研究室はいずれも特定のテーマについて学びを深めるという点で共通しています。しかし、ゼミは学習の機会、授業形式であって場所ではありません。その一方で研究室は実際に研究をするための部屋であり場所です。
理系の研究では実験装置や薬品が必要になるケースが多く、理系の学生は基本的に設備を利用できる研究室に配属される傾向にあります。
研究室では実験だけが行われるのでなく、教授と学生の間で討論や発表なども実施されます。つまり、研究室の中でもゼミが行われるということです。授業と場所の観点から考えると両者の違いがより明確になるでしょう。
ゼミの活動内容の例
ゼミについて理解を深めるには、具体的に大学で行われているゼミの活動内容を知ることが近道です。ここでは、専修大学や千葉商科大学、近畿大学などを例にゼミの活動内容をご紹介します。
専修大学のゼミ
専修大学では「経済データ分析」という名称のゼミ(所属:経済学部国際経済学科)が開講されています。データに基づき経済や社会が抱える諸課題を分析して処方箋を考える文系のゼミです。ゼミ生の人数は30名程度となっており、毎週月曜日の4・5時限に実施されています。
2年生は経済理論と実証分析の方法を学習して、3・4年生は2年次に学んだことを応用して各自のテーマに基づく研究を進める活動内容です。
専修大学の偏差値や特徴、就職先、著名な卒業生などについて知りたい方は下記の記事をご覧ください。
日東駒専とは!各大学の偏差値や学校の特徴、就職先、著名な卒業生について紹介!
千葉商科大学のゼミ
千葉商科大学の政策情報学部では「快適で住みやすい都市空間のデザイン」という研究テーマのゼミが開講されています。
快適で住みやすい都市空間のデザインに関する基礎的理解を深めるために、都市やまちづくりの現場を訪れて公共空間と人の行動を観察するフィールドワークに参加します。
フィールドワークを通して培った問題意識や興味に基づき各自で卒業研究のテーマを設定して、計画的に調査および論文の執筆を進める活動内容です。クラスでは各自のテーマや研究の進め方や論文の書き方などについても議論します。
近畿大学のゼミ
近畿大学の文化・歴史学科では「中国の歴史と文化」というテーマのゼミがあります。中国に興味がある学生が集まるゼミとなっており、中国の歴史・現在・未来、日本との違いなどについて学べます。
3年生では中国に関する必須文献の読会に参加し、4年生では実際の資料・史料を分析して各自の研究を完成させる活動内容です。
近畿大学の偏差値や特徴、就職先、著名な卒業生などについて知りたい方は下記の記事をご覧ください。
産近甲龍とは!各大学の偏差値や特徴、就職先、著名な卒業生について紹介!
高校生がゼミを知っておくべき理由
高校生のうちからゼミについて考えるのは早いと思う方もいるかもしれません。しかし、ゼミについて理解しておくことで大学受験や就職を有利に進められる可能性があります。ここでは高校生がゼミを知っておくべき理由について解説します。
志望校を決めやすくなる
大学の数はたくさんあって志望校を絞るのが難しく感じる方もいるでしょう。
その点、高校生の段階で自分が勉強したいことや興味のあることに挑戦できるゼミ、研究室が見つかれば、志望校を決めやすくなります。志望校を早く決めることができれば受験対策にも集中しやすくなり、大学受験が成功する可能性も大幅に高まります。
オープンキャンパスでゼミ体験ができる大学もあるので、チャンスがあれば率先して参加してみるとよいでしょう。
就職を見据えて進路を決められる
大学のゼミでは、卒業研究をしながら卒業論文や制作物などの成果物を完成させて発表するのが一般的です。
卒業論文や制作物は、就職の書類選考や面接で、大学4年間で習得した専門分野をアピールするための強力な武器となります。
高校生のうちから大学のゼミを調べておくことで、就職活動を有利に進める道筋を描きながら志望校を決められます。将来的に就職活動でアピール材料が不足する事態を回避できるでしょう。
推薦入試における志望理由が明確になる
近年受験者数が増えている総合型選抜入試や学校推薦型選抜入試などでは、書類選考や面接で志望理由が問われます。
その点、入りたいゼミが見つかれば「〇〇ゼミで□□を研究したい」という大学受験における志望理由の軸が定まります。
ゼミを想定した志望理由であれば、大学側としても入学後に学生が勉学に励むイメージが湧きやすくなり、選考を通過させやすくなるはずです。
ゼミを担当する教授の専門分野や所属学会、著書、論文歴、学会発表などの情報をリサーチすれば、さらに説得力と熱意にあふれる志望理由を準備できるでしょう。
総合型選抜入試の早期対策については下記の記事を参考にしてみてください。
総合型選抜入試を制するためには書類審査と小論文の早期対策が必須!
総合型選抜・学校推薦型選抜入試の志望理由書の書き方を徹底解説!【例文あり】
大学でゼミに入らないことはできる?
結論として、大学で必修とされていない限りゼミに入らないことは可能です。特に文系学部の場合はゼミに参加しなくても卒業できることがあります。
ただし、就職の観点からはゼミに入るメリットはとてつもなく大きいです。
ゼミでは、同じ業界を志望する同期の学生と一緒に就職活動に取り組むほか、すでに就職しているOB・OGなどと接点を持てます。ゼミならではの情報ネットワークにより、就職情報を入手しやすくなる点で、就職活動を有利に進めやすいです。
大学のホームページでは、ゼミ生の内定実績や具体的な就職先、就職支援まで紹介されることもあります。例として静岡産業大学のゼミでは、明治安田生命総合職の内定実績があるとのことです。ゼミの内定実績から逆算して志望校を選ぶこともできるでしょう。
ゼミに入らないと就職できないということはありませんが、少なくとも面接で大学で学んだことを伝えやすくなるのも確かです。高校生の段階で就職に有利なゼミを見つけて、志望校に入学したあとゼミに所属できれば、就職活動のハードルは大幅に低くなります。
高校生が志望校の選び方に迷ったときは、ひとまずゼミに入ることを視野に入れて、進路を決めましょう。
まとめ
高校生にとって志望校に合格することはゴールではありません。大学で人々の役に立つ知識とスキルを習得して、社会で活躍できる人材になることが本質的に重要です。
その点、大学のゼミは学問を応用して社会に役立てる研究をする学びの機会です。将来の働き方を充実させるためには、大学受験でゼミを意識した志望校選びをするのが望ましいといえます。
とはいえ、膨大なゼミの情報をリサーチして志望校を選ぶのは簡単ではありません。進路に詳しい教育の専門家にアドバイスをもらうと効率的に志望校を絞り込めます。
ゼミを意識した志望校選びを相談したい方は弊社ホームページにて。