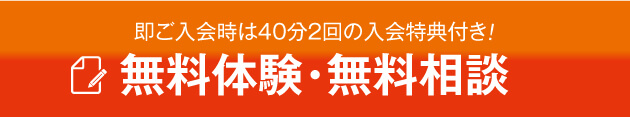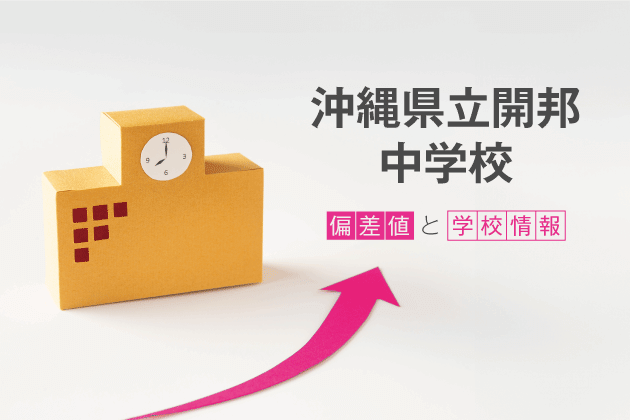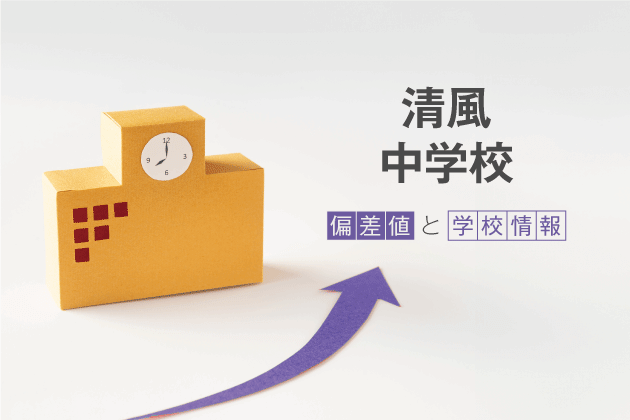赤点(欠点)は、学生であれば誰しも避けたい得点であり、日ごろから対策をすべき対象です。ただ、赤点の概要とともにリスクを把握しておかないと、危機感が薄れて対策を怠ってしまうこともあります。今回は、赤点の意味や基準、デメリットなどを解説するとともに回避方法についてお伝えします。赤点が心配な方、対策方法を知りたい方などはぜひご一読ください。
目次
赤点(欠点)とは
赤点は当たり前のように使われる言葉ですが、具体的な意味を問われると説明しづらい言葉でもあります。まずは赤点の意味について確認してみましょう。
意味
赤点とは、学校の試験結果において学校が求める学力に到達していない点数です。
試験に合格できない点数、不合格の点数を意味する落第点と同じ言葉として知られており、「試験で赤点を取ってしまった」のように学生の間でよく使われます。
落第点は成績表に赤字で記載されることから、「赤」という文字が使われるようになったようです。
なお赤点は、学校によっては欠点と呼ばれることもありますが、それぞれに違いがあるというわけではありません。
赤点は何点から?
赤点は不合格を意味する点数であることをお伝えしました。ただ、赤点は何点なのかイメージできない方もいるでしょう。
赤点は何点からなのかわかるように基準を解説します。
基準
赤点の基準については、一般的に30点未満が設定されやすいといわれています。平均点の半分以下の点数が赤点とされることもあるようです。
学校や教科によって異なる場合もあります。勉強が苦手でテストの結果に不安がある方は、早い段階で赤点の基準について先生に教えてもらうとよいでしょう。
なお、義務教育を受けている段階の中学生に関しては、一般的に赤点はないといわれています。ただ、平均点を大幅に下回っている場合は、直感的に赤点であると判断するお子様、保護者様もいるでしょう。
赤点をとったらどうなる?デメリットは??
赤点の基準についてお伝えしましたが、赤点をとったら最終的にどうなるのか気になったのではないでしょうか。
赤点をとったらどうなるのかわかるように、主なデメリットについて解説します。
留年や退学の可能性が高まる
赤点をとると進級できず原級に留まる可能性も出てきます。いわゆる留年です。学校によっては、学校への適性がなかったと判断され、留年させずに退学を勧められることもあるようです。
補習や追試を受けなくてはならない
赤点をとった場合は、赤点を解消するための補習や追試などを受講しなければなりません。ほかの生徒が新しいことを順調に学んでいく一方で、自分だけ補習や追試を受けるのは大きな負担となるでしょう。
推薦入試の出願に影響する
赤点をとると内申書の成績が悪くなります。推薦入試などでは、内申点が出願の条件となることもあるため、出願が難しくなります。進路の選択肢を減らさないためにも赤点は回避したいところです。
推薦入試について概要を知りたい方は下記の記事を参考にしてみてください。
学校推薦型選抜入試とは?種類や対策、受かる人、落ちる確率などを解説!
奨学金を受けられない可能性がある
奨学金制度では、受給にあたって成績の基準が設定されることもあります。たとえば、5段階評価のうち3.5以上の成績が求められる場合も少なくありません。赤点をとると大学に進学するにあたって奨学金を申請できなくなる恐れがあります。
すでに奨学金を受給して高校生活を過ごしている方であれば、受給中に停止される恐れもあります。
赤点を回避する方法
赤点をとると不利な状況に陥ることがおわかりいただけたでしょう。進路に悪影響を及ぼさないためにも、日ごろから対策を講じて赤点を回避することが重要です。
引き続き赤点を回避する方法について解説します。
学校の授業を真剣に受ける
赤点を回避する方法として最も重要なのが、日頃から学校の授業を真剣に受けることです。
授業を集中して聞かなかったり、寝てしまったりすると、重要な基礎知識が抜け落ちてしまい、その後の授業を理解できなくなることもあります。授業についていけなくなれば、テストで赤点をとるリスクも高くなります。
体調とやる気をしっかり管理して、学校の授業を真面目に受けましょう。
親子で協力して定期テストに挑む
親子で協力して定期テストに挑むことで赤点を回避できる可能性もあります。
たとえば、スマートフォンでゲームやチャットをしないように、テスト期間だけデバイスを保護者様が管理するサポートを検討できます。勉強に専念しやすくなるため、得点アップを狙いやすくなるでしょう。
定期テストにおける親のサポートについて詳しく知りたい方は下記の記事もぜひ参考にしてみてください。
中学生の定期テストに必要な親のサポート8選! やってはいけないNG行動も理由とともに解説
テスト前日まであきらめない
テスト前日の努力によって赤点を回避することも可能です。
学校のテストでは暗記で回答できる問題もたくさん出題されるからです。たとえば、英単語や歴史の年表、漢字などは覚えるだけで得点源になります。
テスト勉強が間に合わずに赤点がよぎったら、最後まで諦めずに暗記だけでも取り組んでみましょう。
定期テストに役立つ暗記方法や科目別の勉強方法については下記の記事でご紹介しています。
定期テストに役立つ暗記方法は? 科目別の勉強法やいつから始めるべきか解説!
ケアレスミスを減らす
ケアレスミスをして赤点になることも十分にあり得ます。理解できている問題をミスして赤点になれば後悔するでしょう。
これまでのテストからミスの傾向を分析すれば、事前に対策をしてミスを減らすことも可能です。
ケアレスミスをなくすための治療法については下記の記事を参考にしてみてください。
ケアレスミスをなくすには? データの蓄積・分析によって減らす治療法を解説!
テストの種類別に対策を把握する
学校では、さまざまな種類のテストが実施され、出題の傾向も異なります。
たとえば、定期テスト以外に単元テストや課題テストなどが実施されることもあります。
テストの種類別に対策を把握しておくことで、得点を獲得しやすくなるでしょう。
単元テストや課題テストの対策については下記の記事で学んでみてください。
課題テストとは? 対策すべき理由や勉強法、結果がやばいときにすることを解説!
単元テストとは? メリット・デメリット、定期テストとの違い、勉強法などを解説!
テストを頑張ったのに赤点…。赤点をとったらすべきことは?
赤点をとってしまったときの回避方法をお伝えしました。ただ、テストを頑張ったのに赤点をとってしまうこともあります。赤点をとったらどうすればよいのでしょうか。
基本的には慌てたり落ち込んだりしないようにします。感情を制御して具体的な対策を検討しましょう。
赤点をとった原因を振り返り、授業態度や勉強時間、学習方法、教材などを見直します。そのうえで、補習や追試を確実に受けて基準をクリアして、赤点を解消していきましょう。ただ、自分だけでは原因が特定できず、対策方法がわからない場合もあります。
必要に応じて学習塾や家庭教師など、外部の教育機関に頼ることも検討しましょう。赤点を克服するためのカリキュラムを組んでもらうことで、不安や心配も和らぎ、落ち着いて対策を進めていけるはずです。
日頃の学習方法をご自身で見直したい方は下記の記事もお役立てください。
赤点をとっても人生終わりではない
赤点をとると、自分は勉強ができないことに絶望して、人生終わりのような気持ちになるかもしれません。自暴自棄になって補習や追試なども受けずに、さらに悪い状況に陥ってしまう方もいるでしょう。
結論として赤点をとっても挽回のチャンスはあります。
苦手分野を特定して地道に克服を繰り返していけば、勉強の苦手意識が払しょくされる日がいつの日かやってきます。
仮に苦手意識が払しょくされなくても、進級して学校を無事に卒業できれば、大学で興味のある学問に出会って勉強が好きになるかもしれませんし、仕事で学ぶことの楽しさと充実感に気づけるかもしれません。
一時的な感情で将来を閉ざさないよう、冷静に今できる対策を始めましょう。
赤点に関するよくあるQ&A
赤点についての理解がだいぶ深まったのではないでしょうか。赤点についてさらに理解を深めるために、赤点に関するよくある疑問にQ&A形式で回答します。
Q1.赤点を2回連続でとるのはやばい?
A1.厳しい学校であれば1回とると留年させられることもあるようです。
したがって、基本的に赤点は1回もとらない覚悟で日頃から勉強に励むことが重要になります。
ただ、補習や追試、提出物などで救済措置を用意してもらえる場合も多いです。
2回連続でとってしまった場合もあきらめず、提示された救済措置に必ず対応しましょう。
Q2.補習をさぼるとどうなる?
A2.進級できなくなるリスクが高まります。
補習は赤点のレベルから脱却するために行われる学習であり、受けなければ現状を改善できるチャンスを失うことになります。
最終的に進級するのが難しく、進路の変更を学校側から打診されてしまうこともあるでしょう。
しっかり補習を受けてやる気を見せることで、先生も最善策を一緒に考えてくれやすくなります。確実に進級するためにも補習をさぼらないようにしましょう。
まとめ
赤点をとってしまう原因は、勉強でわからないことを放置してしまうことです。わからないときすぐに質問できる環境を整えておけば、赤点を回避できる可能性は高くなるでしょう。
オンライン家庭教師であれば、映像通話システムによって自宅で気軽に講師と対面できます。疑問を解消しやすくなり、勉強につまずくリスクを減らせるでしょう。
赤点を回避するためにオンライン家庭教師の利用を検討される方はAxisのオンライン家庭教師ホームページにて。
とは?何点から?.png)