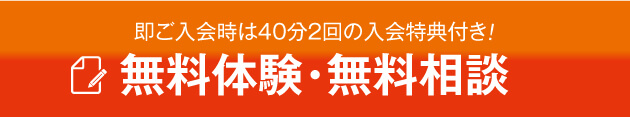2022年4月より高校で「情報Ⅰ」の授業がはじまりました。中間・期末テスト対策のご相談も増えてきています。
そこで今回は、情報Ⅰの内容と中間テスト・期末テストといった定期テスト対策の方法をお伝えします。今後のテスト勉強にぜひご活用ください。
目次
情報Ⅰの内容
情報の授業は、2022年度から急にはじまったように見えますが、実は2003年から行われています。2022年からの情報Ⅰと情報Ⅱは、2021年以前の情報の授業にくらべて内容が増え、より実践的になりました。
この背景には、現在の社会が情報技術をベースに成り立っているという特徴があります。そのため、社会のなかでIT技術がどのように使われているかを知り、どう使えば生活がさらに便利になるかを考え実践できる人材が必要とされています。
4つの学習テーマ
情報Ⅰは4つの学習テーマからなります。各テーマの学習項目を表にまとめました。
| 学習項目 | 学習の種類 | |
| ①情報社会の問題解決 | 情報とは何か・情報の種類と検証・さまざまなメディア・
いろいろな表現形式・問題解決のプロセス・ 情報社会の進展・情報社会を支える法律・個人情報・ プライバシーや肖像に関する権利・知的財産権・ 著作権・著作権の侵害、引用・情報セキュリティ・ 情報セキュリティへの脅威・ユーザ認証とアクセス制御・ パスワードに関する注意事項・ 情報セキュリティを脅かす事例・コンピュータウイルスとその対策・架空請求とその対策・情報の不正な入手とその対策 人工知能の活用・ユビキタスコンピューティング・ 情報技術がもたらす社会の変化・情報技術がもたらす生活の変化・炎上・さまざまなトラブル・迷惑な情報・ 情報を発信するときの注意 |
知識系 |
| ②情報デザイン | アナログとデジタル・デジタル情報の特徴・
ビットとバイト・2進法と10進法・デジタル情報・ 音のデジタル化・画像のデジタル化・解像度・色の表現・ コンピュータグラフィックス・動画のしくみ・ データの圧縮・データの種類と圧縮・ 通信とその発展・マスコミュニケーションの進展・ メディアの性質や特徴・情報の発信方法・ 情報の抽象化、構造化・情報の可視化・ アフォーダンストユーザインタフェース・デザインの工夫・ プレゼンテーションの流れと注意点・スライドの工夫の例・ プレゼンテーションの注意点・発表、評価 |
知識系 |
| ③プログラミング | コンピュータ・ハードウェアとプログラムの実行
OSとアプリケーションプログラム・ファイルとフォルダ コンピュータが扱うデータ、2の補数表現・コンピュータが表現できる限界、誤差・アルゴリズム・アルゴリズムの表現 アルゴリズムとプログラム・人の話す言語との違い 文字を表示するプログラム・計算を行うプログラム 条件分岐式・くりかえし命令・配列・関数 モデル化・モデル作成のプロセス・シミュレーションが行われる例・論理モデルのシミュレーションの例 |
実践系 |
| ④データの活用 | コンピュータネットワーク・無線LANとモバイル通信・
身近なプロトコル例・インターネットのプロトコル・ パケットによる通信・回線交換とパケット通信・ IPアドレスとドメイン名・DNS・WWWとURL・電子メール・暗号のしくみ・共通鍵暗号と公開鍵暗号・ データとデータベース・データベースの管理・ さまざまな情報システム・情報システムの連携の例・ データの形式・データの収集とデータの種類・ データの整理、度数分布表とヒストグラム・代表値・ 四分位数と箱ひげ図・表計算ソフトウェアで分散と標準偏・差を求める・表計算ソフトで散布図と相関係数を求める・ テキストマイニング |
実践系 |
出典:「情報Ⅰ NEXT」(数研出版)より
高校1年生もしくは2年生で、1年間かけてこの内容を勉強します。
上記の4つの章は、大きく2つの種類にわかれます。「①情報社会の問題解決」と「②情報デザイン」は知識分野で、「③プログラミング」と「④データの活用」はプログラミングの基本技術の実践です。
知識系の章では、情報技術が社会でどのような影響があり、良い部分と気をつける部分は何なのかを教わります。情報技術を活用するにあたって、必ず知っておくべき知識をまず身につけます。
その知識を持ったうえで実践系の範囲に移り、社会における問題の発見・解決のための基本的なプログラミング技術を習得します。
このように、情報Ⅰは2段階の学習段階からなります。各段階で学習内容がわかれるため、学び方も変わります。知識系はインプット中心なので、難易度は非常に低いです。ただし、実践系の範囲は注意が必要です。
個人差がひろがる
「③プログラミング」と「④データの活用」の実践系の範囲は、知識として知っているだけでは使えません。とにかく実践が必要です。実践次第で習得度が大きくかわります。
そして情報技術の実践については、生徒・先生のどちらも「個人差がきわめて大きい」という特徴があります。というのも、ほかの科目と違って、情報技術は日常生活で直接使うからです。日常的に使うので、興味を持って積極的に使いこなしている人もいます。なかには、情報Ⅰの教科書に書いてある範囲の技術をすでに持っている人もいます。
教科書を読んではじめて知る人と、すでに教科書以上の技術を持っている人とでは、実践系の知識・技術で個人差が非常に大きいです。
同じことが学校の先生にも言えます。先生も人間ですから、ITに強い人と強くない人がいます。情報科の免許を持っている先生のなかで、情報科の専任の先生はそもそも2割しかいません。授業を実施する側の先生の知識・技術もまちまちですから、授業を受けて伸びる生徒・伸び悩む生徒の差も生まれるかもしれません。
また、プログラミングを教える時間は非常に短く、情報Ⅰ全体の12分の1程度です。授業時間にすると、6時間程度しかありません。
2022年時点の高校生は小学校や中学校でプログラミングを教わっていません。情報Ⅰの授業ではじめてプログラミングに触れる人もいるでしょう。
そうしたプログラミング初心者がわずか6時間の授業で、日常的に趣味でプログラミングをしている人に追いつけるかというと、相当むずかしいはずです。
情報Ⅰの中間・期末テスト対策
では、どうすれば情報Ⅰの中間・期末テストで高得点を取れるようになるか。
前述のように、情報Ⅰは「知識系」と「実践系」でわかれています。それぞれの分野の特徴にあわせてテスト対策をしましょう。
「情報社会」と「情報デザイン」は暗記
まず、知識分野である「①情報社会の問題解決」と「②情報デザイン」は、生物や地歴公民と同じく、暗記科目です。暗記で乗り切れます。
ほかの暗記科目にくらべて非常に易しく、暗記内容も限られています。中間・期末テストを受けた人はわかるでしょうが、テストの問題もむずかしくありません。「知っているかどうか」が問われる範囲なので、むずかしくしようがないのです。
問題集がまだまだ少ないですが、少しずつ出てきています。教科書を中心に、問題集も使って、一問一答形式で暗記しましょう。満点も取れる範囲です。指定校推薦をねらっている人にとっては、「落としてはいけない科目」になります。
「プログラミング」と「データ活用」は課外活動中心
では、個人差が大きく授業時間の少ない「③プログラミング」と「④データの活用」はどうすればいいか。
学校の授業時間だけで乗り切るのはむずかしいかもしれません。学校外でプログラミングに触れる時間をつくりましょう。プログラミングの教室を利用したり、個人で使ってみたりしましょう。実際にプログラミングをする頻度が重要です。
そもそも情報Ⅰは、既定の知識や技術を身につけることが目的ではありません。日常生活や社会の課題を発見し、解決のための手段を生み出せるようになることが目的です。
学校で習った内容の復習をかねて、自分で実際にプログラムを書いてみましょう。プログラムが思ったとおりに動かないこともよくあります。試行錯誤するうちに、上達していきます。
特に大切なのが、「遊び心」です。文字のフォントを大きくしてみたらどうなるかな?動きをつけてみたらどうなるかな?と、既定の学習内容を越えて自由にプログラムをいじってみてください。遊びの繰り返しでプログラムの構造理解が進み、応用がきくようになります。
学校の端末やネット環境によっては、1台の端末を生徒2人で一緒につかう場合もあります。相手に気をつかいながらプログラミングするより、1人で自由に実技をこなすほうが効率は高いでしょう。
中間・期末テストでは、生徒間で極力有利不利がないデータ(人口動態や地域の経済活動などのデータ)を使った問題が予想されます。できるだけ試行錯誤してプログラムの構築ルール・活用方法を理解すれば、そうしたなじみの薄いテーマに対しても対応しやすくなります。
まとめ
いかがでしょうか。情報Ⅰの知識系分野は一問一答形式で暗記をコツコツがんばりましょう。満点を取って、総合成績を押し上げたいところです。
逆に、プログラミングを含む実践系分野は、学校の授業中心では対策が追いつかないと思われます。学校で習う前に、できるだけ早い時期から自由にプログラミングできる環境を整えておきましょう。
情報Ⅰに限らず、中間・期末テストは直前にあわてて対策するよりも前もって計画的に動いておくほうが断然有利です。
相談をされたい方は、弊社のホームページよりお問い合わせください。
共通テストの「情報Ⅰ」について知りたい方は、以下の記事も参考にしてみてください。