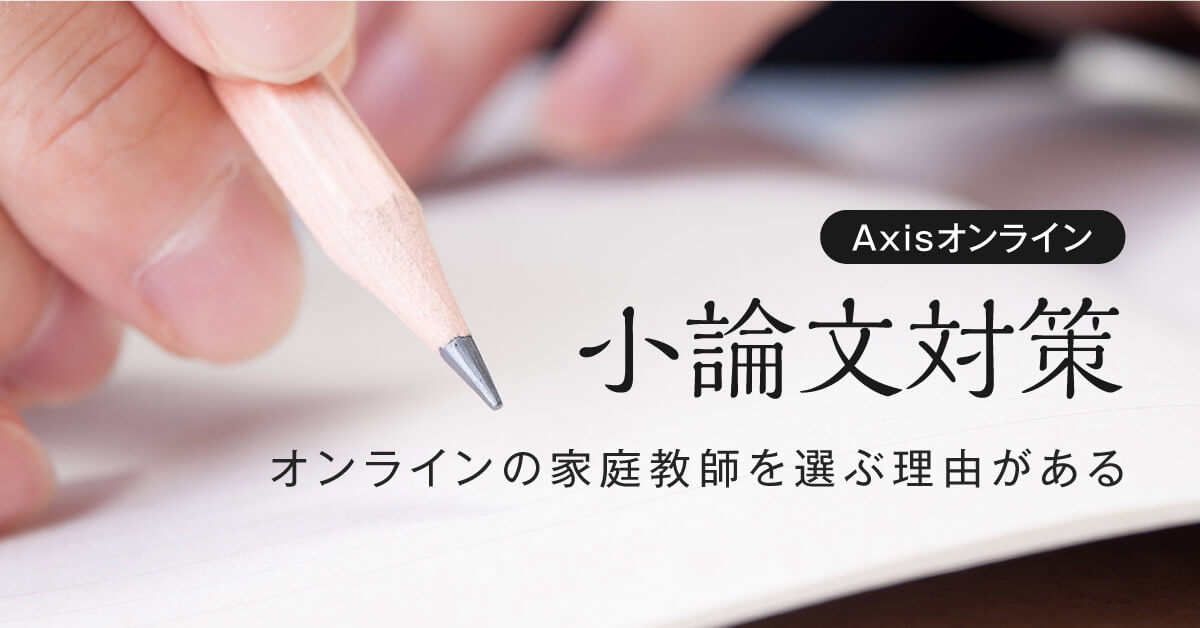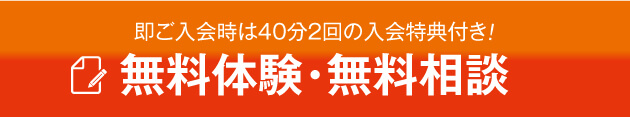大学入試改革により、2021年度入試より小論文を入試科目として採用する大学が急増しました。実際にどういうテーマが出題されていたのかを紹介します。今後の受験勉強にぜひご活用ください。
2018、2019、2021、2022年度の北海道大学の小論文テーマ
2018、2019、2021、2022年度の北海道大学の小論文テーマ一覧は以下のとおりです。なお、2020年度はコロナ禍で後期入試がありませんでした。
| 年度 | 学部・学科(試験種別) | 小論文の種類 | テーマ |
| 2022 | 文学部(一般入試後期) | 課題文読み取り型・教科型・資料読み取り型 | 問題1. 以下は、著者(大学教員)が「大代」という集落でフィールド実習を行う中で考えたことを記した文章である。これを読んで、後の問いに答えなさい。なお、本文に元々書かれていた、生物学者J. フォン・ユクスキュルの説明を(別の筆者による)英文に差し替えている。
(出典:Uexkull, Jakob Johann von, encyclopedia.com 一部改変) 問1. (1)下線部①「生物学者J. フォン・ユクスキュルはそれを『環世界』(Umwelt)と名付ける」について、「環世界」とはどのようなものか、英文を参考にして150字以内で説明しなさい。 (2)下線部②「人間として『よく生きる』という課題には、このような原理的な問題がつきまとう」とはどういうことか。動物の場合と比較して、150字以内で説明しなさい。 問2. 筆者の言う「『よく生きる』こと」について、あなたの考えを、具体例を挙げて500字以内で述べなさい。 問題2. 次の文章と図1、およびそれに関連する図2~4を読んで、日本語で問いに答えなさい。 出典:内閣府『(英語版)幸福度に関する研究会報告――幸福度指標試案―』 図1:Trends of well-being in Japan 図2:Factors that are considered as important to determine happiness 図3:Subjective happiness by age in comparison with the U.S. 図4:Motivation towards engagement with social activities 問1. (1)下線部”paradox of happiness”について、本文と図1に基づいて150字以内で説明しなさい。 (2)本文では幸福度指標を作成することについての意義についてどのように述べられているか、150字以内で説明しなさい。 問2. 本文と複数の図の内容を踏まえ、幸福度を高める条件を指摘し、それを実現する方法についてあなたの考えを500字以内で述べなさい。 |
| 教育学部(一般入試後期) | 課題文読み取り型 | 問題1. 以下の文章は、山岸俊男著『日本の「安心」はなぜ、消えたのか―社会心理学から見た現代日本の問題点』の一部である。これを読んで、次の問いに答えなさい。
問. 筆者が述べる「臨海質量」という考え方を整理し、現代社会における問題をこの概念を用いて800字以内(句読点を含む)で論じなさい。具体的な社会問題を例示する際は、本文内で取り上げられているいじめ問題でも、その他の問題でも構いません。 問題2. 以下の文章は、東畑開人著『居るのはつらいよ―ケアとセラピーについての覚書』の一部である。これを読んで、次の問に答えなさい。 問. 著者は「僕らは二つの時間を生きている」と述べている。この「二つの時間」というとらえ方をふまえて教育のあり方を考えるならば、どのようなことがいえるか。あなたの考えを800字以内(句読点を含む)で述べなさい。 |
|
| 法学部(一般入試後期) | 課題文読み取り型 | 問題1. 次の文章を読んで、問いに答えなさい。
出典:山本圭著『現代民主主義』 問1. 熟議民主主義および闘技民主主義の内容を300字以内で説明しなさい。 問2. 闘技民主主義による熟議民主主義に対する批判についてどのように考えるか、あなたの意見を500字以内で論じなさい。 問題2. 次の文章を読んで、問いに答えなさい。 出典:矢作弘著『都市危機のアメリカ』 問1. アメリカにおいてジェントリフィケーションはどのように変遷したか。コミュニティとの関わりに言及しつつ、250字以内で説明しなさい。 問2. ジェントリフィケーションが起こる原因に関して、消費サイド説と生産サイド説のいずれに説得力があると考えるか、あなたの意見を500字以内で論じなさい。 |
|
| 経済学部(一般入試後期) | 課題文読み取り型 | 問題. 次の3つの文章を読んで、(1)から(3)の問題にすべて答えなさい。
(出典) 文章1:宮崎雅人著『地球衰退』 文章2:小磯修二著『地方の論理』 文章3:枝廣淳子著『地元経済を創りなおす―分析・診断・対策―』 (1)文章1と文章2に則して、東京一極集中の要因と問題点について300-400字以内でまとめなさい。 (2)文章3で説明されている、地元経済の活性化に取り組む際の留意点を300-400字以内でまとめなさい。 (3)文章1から文章3の内容を踏まえて、日本における望ましい地域経済のあり方について、あなたの考えを述べなさい。解答の際には、地域や産業に則した具体的ないアイディアを提示しながら、700-800字以内で記述しなさい。 |
|
| 2021 | 教育学部(一般入試後期) | 課題文読み取り型 | 問題. 下條信輔著『ブラックボックス化する現代―変容する潜在認知』を読んで、下線部「オリンピックのはらむ問題とパラリンピックのそれとは、本質的に連続的なものだ」という筆者の主張について整理したうえで、それに対するあなたの意見を800字以内で述べてください。 |
| 法学部
(一般入試後期) |
課題文読み取り型 | 問題. 前田健太郎著『女性のいない民主主義』を読んで、
(1)下線部「むしろ、アメリカは民主主義国と呼ぶには値しないと言い切ってしまった方が、民主主義を定義する上では価値があるのではないか」とあるが、なぜそう言えるのか。シュンペーターの「民主主義の最小定義」の内容を明らかにした上で、250字以内で説明しなさい。 (2)ダールの「ポリアーキー概念」とシュンペーターの「民主主義の最小定義」にはいかなる共通点と相違点があるか。本文に即して500字以内で説明しなさい。 |
|
| 経済学部(一般入試後期) | 課題文読み取り型 | 問題. 西内啓著『統計学が最強の学問である:データ社会を生き抜くための武器と教養』(文章1)、ジョエル・ベスト著、林大訳『統計はこうしてウソをつく:だまされないための統計学入門』(文章2)、田村秀著『データの罠:世論はこうしてつくられる』(文章3)、デアリー・スミス著、川添節子訳『データは騙る:改竄・捏造・不正を見抜く統計学』(文章4)を読んで、
(1)文章1と文章2で説明されている、社会における統計や統計学の意義についてまとめなさい。その際には、2つの文章の共通点と相違点が明確になるように300-400字以内で記述しなさい。 (2)文章3と文章4に即して、わたしたちが社会の統計データを分析、利用する際に留意すべき点を300-400字以内でまとめなさい。 (3)文章1から文章4までで説明された、統計の意義と限界を踏まえて、行政による政策や企業の戦略がどのように立てられていくべきか、あなたの意見を述べなさい。解答の際には、自らの意見について理由を挙げながら、700-800字以内で説明しなさい。 |
|
| 2019 | 教育学部(一般入試後期) | 課題文読み取り型 | 問題1. 鈴木啓嗣著『子どものための小さな援助論』を読んで、次の問いに答えなさい。
(1)筆者は下線部において、援助者の立場にありながら、「援助という関係そのものに危うさを感じている」と主張している。この根拠について触れつつ、子どもへの援助に対して自らの考えを1000字以内で論じなさい。 問題2. 苅谷剛彦著『イギリスの大学・ニッポンの大学―カレッジ、チュートリアル、エリート教育』を読んで、次の問いに答えなさい。 (1)イギリス流エリート教育の「奥行き」に関する筆者の主張を踏まえて、今後の日本の大学教育のあり方について自らの考えを1000字以内でろんじなさい。 |
| 法学部
(一般入試後期) |
課題文読み取り型 | 問題1. 瀧川裕英著「神は国境を引くか?」を読んで、問いに答えなさい。
(1)グディンの割当責任モデルによると、国境が引かれるのはなぜか。配慮の希薄化が起こる理由を考えつつ、250字以内で説明しなさい。 (2)地球の最善の統治のために、国境はどのように引かれるべきか。統治担当者と統治責任者の違いを踏まえて筆者の主張を500字以内で説明しなさい。 問題2. 蟻川恒正著「尊厳と身分」を読んで、問いに答える。 (1)下線部①について、「走れメロス」を友情物語に帰すべきでない理由は何か。筆者の主張を250字以内で説明しなさい。 (2)下線部②について、出頭保証人制度の基本的同一性を維持したまま、その適用を貴族以外の者にまで拡張した場合、「公共的義務」と個人の自由の関係にどのような変化が生じる危険性があると考えられるか。500字以内で説明しなさい。 |
|
| 経済学部(一般入試後期) | 課題文読み取り型・資料読み取り型 | 問題1. 文章1(伊丹敬之『日本型コーポレートガバナンス―従業員主権企業の論理と改革―』(日本経済新聞社))は会社の主権者として従業員がふさわしいことを主張している。文章2(岩田規久男著『そもそも株式会社とは』)は文章1を批判的に検証検討したものである。2つの文章を読んで、2つの設問に答えなさい。
(1)文章1を読んで、なぜ会社の主権者として従業員がふさわしいのか、筆者の主張を400-500字以内でまとめさない。 (2)文章2では、従業員を会社の主権者とすることについて、さまざまな観点から批判的に検討している。文章1も踏まえて、従業員を会社の主権者とすることの妥当性について、あなたの意見を400-500字以内で述べなさい。 問題.2 次の文章を読んで、(1)と(2)の2つの設問に答えなさい。 ワーク・ライフ・バランスとは、「仕事と生活の調和」を意味し、内閣府ではワーク・ライフ・バランスが実現された社会を「国民一人ひとりがやりがいや充実感を感じながら働き、仕事上の責任を果たすとともに、家庭や地域生活などにおいても、子育て期、中高年期といった人生の各段階に応じて多様な生き方が選択・実現できる社会」と定義している。具体的には、子育てや親の介護が必要な時期など個人の置かれた状況に応じて多様で柔軟な働き方が選択できることなどがあげられる。 (1)資料1から資料5(OECD、総務省、厚生労働省の飼料をもとに作成)にもとづき、諸外国と比較した際の日本の労働時間の特長と、2002年以降の日本の労働時間の推移と特徴について400-500字以内で説明しなさい。なお、すべての資料を参照する必要はないが、どの資料を参照したかを解答の中で明記すること。 (2)資料6から資料12(厚生労働省、三菱UFJリサーチ&コンサルティング、内閣府、内閣府男女共同参画局の資料をもとに作成)にもとづき、日本においてワーク・ライフ・バランスを実現するための課題と、その課題への対策について、あなたの考えを400-500字以内で述べなさい。なお、すべての資料を参照する必要はないが、どの資料を参照したかを解答の中で明記すること。 |
|
| 2018 | 教育学部(一般入試後期) | 課題文読み取り型 | 問題1. 子安潤著『授業における中立性と公正さ』を読んで、筆者の主張と自身の経験を照らし合わせ、学校教育に関する自分の考えを1000字以内で論じる。
問題2. 帚木蓬生著『ネガティブ・ケイパビリティ』を読んで、現代社会を生きていくうえで、「素養や教養」はなぜ大切なのか、その理由について1000字以内で論じる。 |
| 法学部
(一般入試後期) |
課題文読み取り型 | 問題1. 柳川範之著「新しいコーポレート・ガバナンスの可能性」を読んで、設問に答える。
(1)傍線部の説明問題に250字以内で答える。 (2)「転職を前提としたチームづくりを推し進めていくと、日本企業の組織とガバナンスの仕組みは大きく変革していくと考えられる」とあるが、筆者が論じるこれからの日本企業のあり方とその利点を500字以内で説明する。 問題2. 齋藤純一著『不平等を考える』を読んで、設問に答える。 (1)筆者は、「マス・デモクラシー」のもとでの「レトリックの作用」に対し、「市民」がどのように対応すべきと述べているか250字以内で説明する。 (2)筆者によれば「熟議」と「人々がいだく感情」の関係は「誤解」されやすいという。なぜ「誤解」が生じやすいのか、またそれに代えて筆者は両者をどのように関連づけているか500字以内で説明する。 |
|
| 経済学部(一般入試後期) | 課題文読み取り型・資料読み取り型 | 問題1. 文章1(鹿野政直著『近代日本思想案内』)と文章2(玉野井芳郎著『日本の経済学』)を読んで、設問に答える。
(1)文章1で指摘されている「翻訳語の世界と日常語の世界という文化の二重構造」の問題は、文章2で取り上げられている「「経済」ということば」をめぐる問題にも当てはまるかどうかについて、400-500字以内で自分の考えを述べる。 (2)文章2のなかで、西洋の経済学説が輸入される際、「われわれの先輩はそうとまどいはしなかったらしい」とされているが、この見解の趣旨を説明し、それについての自分の考えを400-500字以内で述べる。 問題2. 複数の資料(出展不明)を踏まえて、設問に答える。 (1)2000年代における日本を訪れる外国人旅行者の推移と特徴について400-500字以内で説明する。 (2)複数の資料を踏まえて、訪日外国人旅行者の日本における消費を増加させるための課題と、その課題への対策について、自分の考えを400-500字以内で述べる。 |
2018、2019、2021、2022年度の北海道大学の小論文傾向
2018-2021年度(2020年度除く)は、教育学部・法学部・経済学部の3学部で、2022年度は文学部を加えた合計4学部の一般入試後期で小論文が出題されました。
小論文の種類は毎年、課題文読み取り型です。本文の下線部の内容説明と、それに基づいて自分の考えを合わせて1000-2000字で記述する問題です。経済学部については2018年度、2019年度で資料の読み取りもありました。また、2022年度から始まった文学部の小論文入試では課題文の1つが英語表記でした(設問と解答は日本語)。
出題テーマは、課題文も図表も各学部の専攻内容に則しています。専門的な知識は特に必要ありません。課題文や図表を見て読み取れる範囲内での解答で十分です。ただ、具体的な社会事象だけでなくやや抽象的なテーマが扱われることも多く、その点は注意が必要です。
新聞やテレビで報道されている硬派なニュースについて、自分なりに考えて意見を持つようにしておきましょう。硬派なニュースというのは、2019年度に北海道大学で出題された、「大学教育のあり方」や「ワーク・ライフ・バランス」などのことです。
賛成・反対の意見だけでなく、「自分がどのように捉えているか」「どうあるべきだと思うか」を言語化しておきましょう。言語化しにくい場合はネットで検索してヒントを見つけましょう。検索するうちに、「これだ!」と思うものが見つかります。
自分の意見を言語化したり、その過程で知識を蓄えるようにしておけば、考え方の道筋が自分の中に出来上がります。それがあれば、初めてのテーマに対しても、すでに知っている内容やそれに対する自分の考えを応用できます。いざ小論文の勉強を本格的に始めたときに対策が非常にスムーズです。
小論文の書き方についてはこちらでも紹介しています。
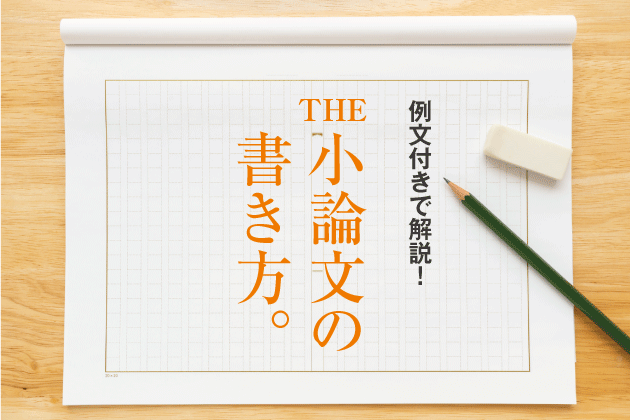 手早く合格を取れる小論文の書き方とは?塾関係者が例文付きで解説!
手早く合格を取れる小論文の書き方とは?塾関係者が例文付きで解説!
まとめ
いかがでしょうか。専門的な知識は不要ですが、やや抽象的なテーマに関して自分の考えを記述する問題が毎回出されています。硬派なニュースを使って自分の考えを持つ練習をしておきましょう。
小論文の対策は大抵、入試3か月前からで間に合いますが、もっと準備期間を必要とする大学もあります。いつから受験対策を始めればいいかご不安な方は、ぜひ弊社のホームページをご覧ください。