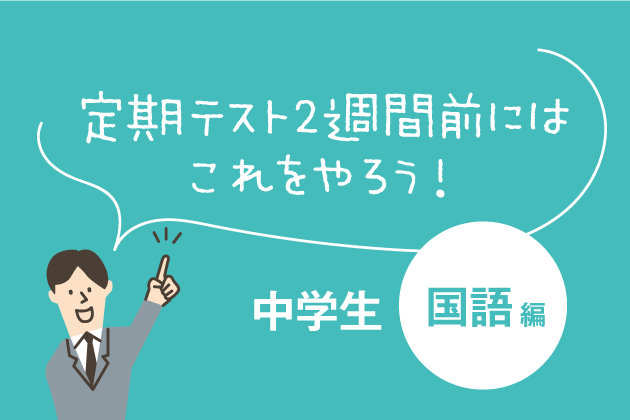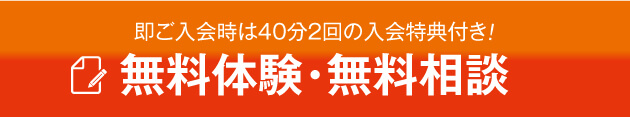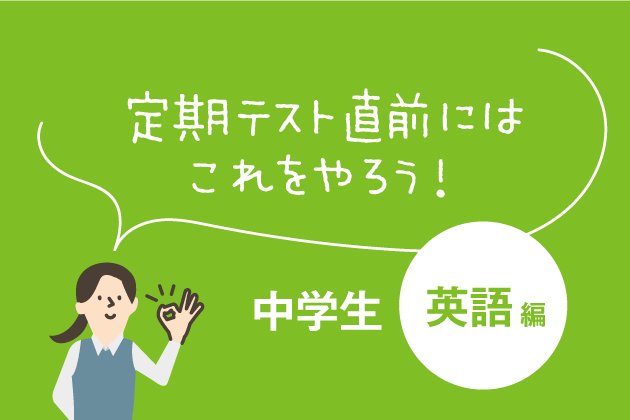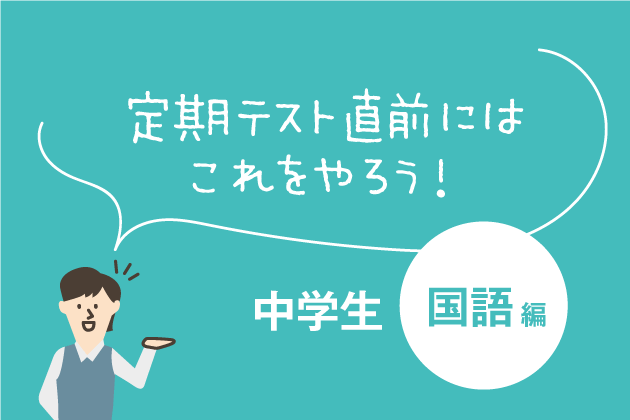中学校の定期テスト対策は、多くの中学生やその保護者の方にとって心配の種ではないでしょうか。今回は、「国語の定期テスト2週間前にやってほしい対策」についてまとめました。国語で困っている人も、もっと高得点を狙いたい人もぜひ参考にしてください。
定期テスト2週間前にはこれをやろう
国語には、「勉強しても上がらない」「答えがひとつではないから勉強しても無駄」という都市伝説があります。実は、定期テスト対策としては5教科の中で最も簡単です。食わず嫌いさえしなければ、こんなにオイシイ教科はありません。ぜひ、下記の手順でテスト対策をしてみてください。
暗記モノで確実に点をかせぐ
まず、漢字の暗記です。これだけで10~20点ありますから、満点をとるつもりで勉強しましょう。
古典を習っているときは古語や月の異名(睦月、如月など)、漢文単語も覚えておきましょう。
暗記手順は以下のとおりです。
①漢字ドリルで毎日10個覚える
満点を取るまで繰り返し漢字の書き取りテストをしてください。間違えた漢字だけでなく、1度正解した漢字もテストしてください。書き取りが出来たら、読み取りのテストもしましょう。
②前日に覚えた漢字を復習する
新たに10個覚えるよりも先に前日覚えた漢字を復習してください。復習方法は前述の①と同じで、全問正解するまでテストです。
③日曜に1週間分を復習する
月曜~土曜に覚えた漢字を全て復習しましょう。前述の②をしておけば、あまり時間がかかりません。日曜に予定がある場合は土曜に復習しておきましょう。
読解問題の解答を理解する
本文の読解問題は、出題範囲や設問が大体決まっています。数が限られていますから、1つ1つ丁寧に理解しましょう。暗記でも対応可能ですが、理解するほうが早いです。
①解答を見る
早速解答を見てください。問題を解かず、解答を読むだけで大丈夫です。
②全問正解するまで問題を解く
次に問題を解きます。大問ごとに全問正解するまで繰り返し問題を解きましょう。
③解答の解説を自分なりにしてみて、ワークの解説と照らし合わせる
正解した問題について、その解説をしてみましょう。解答の根拠を本文中から探し出したり、自分の言葉で説明してみたりします。それができたら、その根拠や説明で合っているかどうかを、ワークの解説と照らし合わせてみましょう。いわば、「解説の答え合わせをする」のです。
解説は丸暗記せず、ポイントを理解するようにしましょう。覚えきれる量ではありませんし、テストではワークと出題の仕方が変わります。ワークで選択問題だった箇所が、テストでは記述問題や書き抜き問題になったりします。解答のポイントさえ分かっていれば、出題形式が変わっても正解できます。
④教科書準拠の市販の問題集を1冊仕上げる
別の問題集でも前述の①~③と同じ流れで対策してください。内容は7割方同じです。ワークでポイントを理解できた問題の練習になりますし、ワークに掲載されていない内容を新たに身に着けられます。
テスト1週間前までに前述の①~③まで仕上げておき、ラスト1週間で暗記モノの確認と前述の④を実施しておきましょう。
国文法は誰かに聞く
国文法は、暗記と理解の両方必要です。それぞれ説明します。
①まず丸暗記する
助詞10個など、暗記しないといけないものはテスト1週間前までに暗記しましょう。これを面倒がる人もいますが、活用表の穴埋め問題が出されることもあります。暗記するだけで楽々と10点以上取れる問題です。
②日常語で理解する
文法問題を解き、解説を読んでもややこしくて理解できない場合もありますよね。例えば、「らしい」という言葉だけで、推定の助動詞、「~らしく」の連用形、形容詞の接尾語などに分かれます。ワークの解説を読んでも、文法が苦手な人にとってはよく分からない場合もよくあります。
そういう場合は誰かに聞きましょう。問題集の解説が分かりにくいのは、「推定」「接尾語」などの文法用語になじみがないからです。いくら的確に説明されても、なじみの薄い言葉だとピンと来ないものです。
国文法を理解している人は、その人なりの日常語を使って理解しています。その説明を聞いておくと、かなり理解しやすくなります。学校のワーク以外に文法の問題集を1冊使うと、さらにしっくりきます。
まとめ
いかがでしょうか。国語は暗記モノである程度点数を稼げる為、全問正解するつもりで挑みましょう。そこからは、本文読解の問題集を2冊使って各設問の解答の根拠を把握しておきましょう。国文法が苦手な人は、誰かに説明してもらうと時短になります。安定して高得点を取りたい人は「Referential Question(指示質問)」を取り入れてみてください。
国語に限らず、定期テストの点数をアップしたい方は、こちらの弊社ホームページをご覧ください。