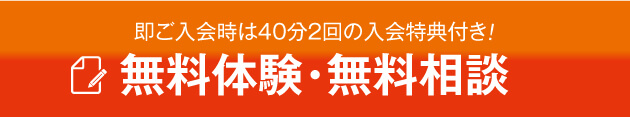大学受験の成功率を高めるうえで、学校推薦型選抜入試も選択肢となります。ごく一部が受験するように思うかもしれませんが、受験者の割合は決して少なくありません。今回は、学校推薦型選抜入試の動向や種類、内容、スケジュール、対策などを解説します。受かる人・落ちる人、落ちる確率に触れているので、受験に迷う方はぜひ参考にしてみてください。
目次
学校推薦型選抜入試とは?
学校推薦型選抜とは、学校長(出身高校)からの推薦を出願条件とする推薦入試です。
まずは、学校推薦型選抜入試の動向や種類、入試内容、スケジュール日程などからご説明します。
近年の動向
近年の大学全体、国立大学における学校推薦型選抜入試・一般選抜入試の割合は下記の通りです。
| 大学全体 | 2022年 | 2023年 |
| 学校推薦型選抜入試 | 31.0% | 30.5% |
| 一般選抜入試 | 49.7% | 48.9% |
大学全体における学校推薦型選抜入試の割合は、一般選抜入試よりも約18%低い程度です。ただ、10人あたり3人以上が利用する受験方式となってきていることから、決してマイナーではないとわかるでしょう。
| 国立大学 | 2022年 | 2023年 |
| 学校推薦型選抜入試 | 23.4% | 23.7% |
| 一般選抜入試 | 57.6% | 57.0% |
国立大学における学校推薦型選抜入試の割合は0.3%増加していました。今後増加傾向が続くようであれば、推薦入試を検討する方も増えていくでしょう。
種類
学校推薦型選抜入試は、指定校制と公募制に分かれています。
| 指定校制 | 大学が指定する高校の生徒だけが受験できる推薦制度 |
| 公募制 | 大学が指定する高校の生徒でなくても出願要件を満たせば誰でも受験できる推薦制度 |
指定校制は高校への信頼関係に基づき実施されるので、合格率は高い傾向にあります。ただし、校内選考を通過しなければなりません。
公募制は基本的に高校ごとの推薦人数が制限されず、指定校制よりも条件が緩和される印象です。ただし、志望者数が多いと合格が難しくなる点には変わりありません。
※公募制でも学部によっては高校ごとに推薦人数が制限されることもあります。
入試内容
学校推薦型選抜の入試内容は、書類審査や面接、小論文などです。グループディスカッションが実施されるケースも少なくありません。
同じ大学であっても学部によって試験内容が異なるケースもあります。
最近では、数英国などの基礎学力テストを課す大学も登場しており、学校推薦型選抜入試でも学力が試されるトレンドも見受けられるようになりました。近畿圏や中京圏の私立大学では、この基礎学力テストを使う推薦入試が定着しているので、このあたりにお住まいの方にはなじみがあるかもしれません。
基礎学力テストの導入事例や対策などについては下記の記事で詳細をご確認ください。
学校推薦型入試に学力は重要? 基礎学力テストの導入事例、対策を解説!
スケジュール日程
学校推薦型選抜入試は、目安として11月ごろに出願受付、試験が行われ、おおよそ12月以降に合格が発表されます。
共通テストを選考に利用するパターンでは、合格発表が2月ごろになります。
指定校推薦の場合は校内選考を経るため、各自で学校のスケジュールを早めに確認しておきましょう。
学校推薦型選抜入試と総合型選抜入試の違い
学校推薦型選抜入試のほかに総合型選抜入試を実施する大学もあります。どちらを受験すべきか適切に判断するには、両者の違いを押さえておくことも重要です。
学校推薦型選抜入試と総合型選抜入試の主な違いは下記の通りです。
| 比較項目 | 学校推薦型選抜入試 | 総合型選抜入試 |
| 概要 | 出身高校からの推薦に基づき受験する入試 | 大学が求める学生像に基づき合否を決める入試 |
| 学校長からの推薦 | 必要 | 不要 |
| 校内選考 | あり(指定校推薦の場合) | なし |
総合型選抜とは、大学が求める学生像に基づき合否を決める入試です。大学が求める学生像は、入学者の受け入れ方針をまとめたアドミッションポリシーで確認できます。
学校推薦型選抜入試と違って、志願者自ら出願できる制度であり、学校長の推薦は基本的に必要ありません。校内選考も基本的に不要で、アドミッションポリシーの内容に合致する方であれば受検の選択肢となります。
総合型選抜入試とアドミッションポリシーについて詳しく知りたい方は下記の記事を参考にしてみてください。
総合型選抜入試とは? 入試内容やスケジュール日程、一般選抜入試との違い、対策などを解説!
総合型選抜対策のキーワード!3ポリシー徹底解説【アドミッション・ポリシーが重要!】
学校推薦型選抜入試の対策
学校推薦型選抜入試は、一般選抜入試と試験内容が大きく異なるため、対策がわかりづらいかもしれません。
ただ、要点を押さえておけば早いうちから準備を進めて有利に受験できます。
ここでは、学校推薦型選抜入試で特に重要となる対策について解説します。
早い段階から志望理由を考えておく
学校推薦型選抜入試の面接において重視されるのが志望理由です。
入学意欲が伝わる志望理由を述べれば合格の可能性が高まります。ただ、大学が納得する志望理由は深い自己分析なくして生まれません。
できれば、高校1年生のころから自分がやりたいこと、好きなこと、将来なりたい職業などを明確にして、希望する目標やキャリア、夢を実現できる学校を見つけ、志望理由をじっくり考えておきましょう。
小論文の添削を受ける
学校推薦型選抜入試では小論文試験が実施されることから小論文対策も必要です。
受験直前に慌てないように、高校1年生・高校2年生のころから文章の書き方や合否を決めるポイントなどを学んでおくのが望ましいでしょう。
小論文で最も基本的な対策はプロから添削を受けることです。論理展開や説得力の出し方、読みやすい表現などを教えてもらうことで、合格水準の文章レベルを目指せます。
部活が忙しい高校生は、無理なく添削を受けられるオンライン講座が特におすすめです。
活動報告書の作成に向けて活動を始める
学校推薦型選抜入試では、活動報告書の提出が求められることもあります。自信を持ってアピールできる活動を高校1年生・高校2年生のころから始めておくことも重要です。
書き方については高校3年生でも十分に間に合うので、出願までに計画的に学んでおきましょう。
活動報告書の書き方は下記の記事で例を含めて紹介しているので参考にしてみてください。
総合型選抜・学校推薦型選抜入試における活動報告書の書き方を徹底解説!【例文あり】
学校の各種テストで高得点を目指す
学校推薦型選抜入試では、調査書における学習成績を示す数値も推薦基準とされます。学校長から推薦を受けるためには学校で好成績を維持することも前提です。
高校3年生の1学期までの成績を評価する大学もあります。最終学年まで油断せず授業に真剣に取り組み、各科目の定期テストや単元テスト、課題テストなどで高得点を目指しましょう。
定期テストや単元テスト、課題テストの対策については下記の記事をお役立てください。
定期テストに役立つ暗記方法は? 科目別の勉強法やいつから始めるべきか解説!
単元テストとは? メリット・デメリット、定期テストとの違い、勉強法などを解説!
課題テストとは? 対策すべき理由や勉強法、結果がやばいときにすることを解説!
学校推薦型選抜入試に受かる人・落ちる人は?
学校推薦型選抜は、人によって相性が大きく左右される入試です。受験を後悔しないためには、受かる人・落ちる人の特徴を把握しておくのが望ましいでしょう。
ここでは、学校推薦型選抜入試に受かる人・落ちる人の特徴をまとめてみます。
受かる人
学校推薦型選抜入試に受かる人の特徴は下記の通りです。
・学校の授業に毎日真剣に取り組んでいる
・周囲から文章がうまいといわれる
・コミュニケーション力や説得力に自信がある
・将来目指している職業が決まっている
・スポーツや芸術など勉強以外に得意なことがある
目的意識を持って充実した学生生活を過ごしている、なおかつ志望理由をしっかり伝えられる言語化能力を持つ方であれば、学校推薦型選抜入試に合格できる可能性は極めて高いです。
落ちる人
学校推薦型選抜入試に落ちる人の特徴は下記の通りです。
・定期テストや単元テスト、課題テストなどの点数が低い
・文章を書くのが苦手
・グループワークで発表を人に任せてしまう
・将来の夢や目標がない
・勉強だけできればよいと考えている
夢や目標を持たず、なんとなく学生生活を過ごしている方は、志望理由を伝えるのに苦労します。勉強ができても学校推薦型入試に合格するのは難しいでしょう。
学校推薦型選抜入試に落ちる確率は?
学校推薦型選抜入試の落ちる確率は、学部によって変わるのが実情です。
合格実績を見ると、受験者の全員が合格し、落ちる確率が0%の学部があります。その一方で、受験者の半分が不合格になり、落ちる確率が50%の学部もあります。
ただし、年度によって受験者数が変わることもありますので、その場合当然ながら合格率は変動します。大学側の合格者数の設定増減でも確率は変わるでしょう。自身ではどうしようもできないところです。
大学、学部の入試結果を確認して、難易度を事前に把握しておくことが重要ですが、受験に向けて、自分でできる準備をしっかりしておくことが肝心です。
まとめ
学校推薦型選抜入試では、出身校の学校長から推薦を受ける必要があるほか、書類審査や面接、小論文など幅広い試験をくぐり抜けなくてはなりません。
計画的に準備しないと対策が間に合わず、受験の機会を失うこともあるでしょう。
何から始めるべきか迷うようであれば、受験の専門家からアドバイスを受けるのがおすすめです。
学校推薦型選抜入試に向けてすぐにでも対策を始めたい方はAxisのオンライン家庭教師ホームページにて。