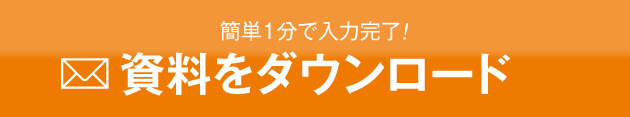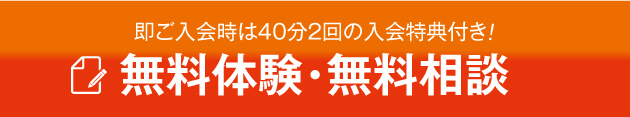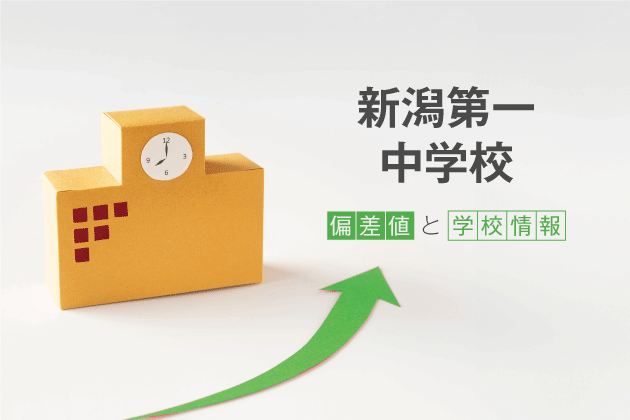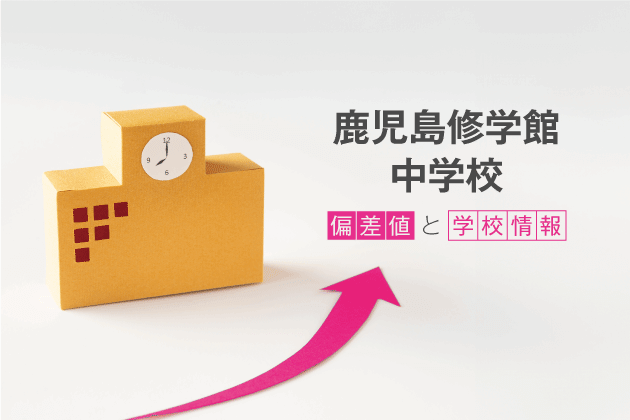大学を目指すときに決める学部は受験生にとって身近な言葉ですが、具体的な意味を聞かれると説明できない方も多いのではないでしょうか。学部について理解を深めることで、進路を決めるときの視野が広がります。今回は大学の学部の意味や学科との違い、種類、学べる内容などを解説します。これから学部を決めようとしている方はぜひ参考にしてみてください。
目次
大学の学部とは?
高校生は大学を志望するときに学部を決めなければなりません。最近では学部に似た組織もさまざま登場しつつあり、それぞれの意味を理解しておかないと、進路の精度が下がる恐れもあります。学部について理解を深められるように、意味や学科との違い、関連する組織について解説します。
意味
大学の学部とは、学問分野によって分類された教育・研究組織です。
大学の学部では教授の授業やゼミなどで学問を学び、4年生になったら研究室に所属して特定のテーマについて研究します。文系・理系によって学部の入試科目が異なります。
基本的には、文系の学部は国語や英語、地歴・公民などの科目で受験し、理系の学部は数学や化学、生物、物理などの科目で受験するのが一般的です。
文系・理系の選択については下記の記事をぜひ参考にしてみてください。
高校生の進路の決め方を解説! 決める上で大切なこと、決める時期は?【進路アドバイス付き】
学科との違い
学部と学科はいずれも教育・研究組織ですが、対象とする学問の範囲に違いがあります。学部のほうが学問の範囲が広く、学科のほうが狭くなります。細分化された学問に対応している組織が学科ということです。
たとえば、理学部であれば理学という学問が物理・化学・数学・生物などに細分化され、物理学科・化学科・数学科・生命理学科などに分類されます。
物理学科に所属する学生は物理をメインとして学びますが、物理だけを学ぶわけではありません。科学史や基礎化学、線形代数学入門、生物学序論など、理学部に共通する教育科目まで学ぶことになります。
学群・学域・学類・学環・学府
学部と学科以外には学群・学域・学類・学環・学府などの組織もあります。
学部と学科に関連する組織についてそれぞれの意味を表にまとめてみます。
| 学群 | さまざまな学問分野を含むように複数の学部を集めた教育・研究組織 |
| 学域・学類 | 境界領域を含んだ広い分野の学問を履修できる教育・研究組織 |
| 学環 | 関連するさまざまな学問を環状につなぐイメージで特定の学問を中心に追究する教育・研究組織 |
| 学府 | 学問を追究する人々が集まる教育・研究組織 |
複数の学問を組みあわせることで新たな知見を得られることもあります。そのため、大学では複数の学問を学びやすいように、学部や学科以外の教育・研究組織を開設することが多いのでしょう。
学部の系統・種類
学部の系統を把握しておくことで、自分が興味のある学部の種類をおおよそ把握しやすくなります。続いては学部の系統・種類について解説します。
あわせて、推薦入試の小論文課題の傾向と対策についてもご紹介いたします。リンク先の記事をご確認ください。
人文科学系
人文科学系は、人間が育んできた文化・思想をあらゆる角度から研究する学問です。具体的な種類としては、文学部や外国語学部、心理学部などが挙げられます。
言語や歴史、思想、心理などを学び、記者や学者、外交官、公認心理士といった職業を目指すことが可能です。
社会科学系
社会科学系は、社会現象や人間社会の構造などを研究する学問です。具体的な種類としては法学部や経済学部、商学部などが挙げられます。
法律や経済、マーケティングなどを学び、弁護士や司法書士、銀行員、マーケターといった職業を目指すことが可能です。
理工学系・医療系
理工学系・医療系は、自然の摂理や機械、人体、治療法などについて研究する学問です。具体的な種類としては、理学部や理工学部、医学部などが挙げられます。
数学や物理、化学、生物をはじめ、機械や電気、解剖、病態などを学び、アナリストやエンジニア、研究員、医者といった職業を目指すことが可能です。
教育系・芸術系・家政系
そのほかにも教育系・芸術系・家政系などさまざまな系統があります。教育系は理想的な教育の在り方を探る学問、芸術系は芸術の理論、美のとらえ方を研究する学問、家政系は日常生活を科学して幸福の創造を目指す学問です。
具体的な種類としては、教育学部や芸術学部、家政学部などが挙げられます。教育論やデザイン、栄養学などを学び、教師や塾講師、アーティスト、管理栄養士、ファッションデザイナーといった職業を目指すことが可能です。
大学の学部選びで押さえるべきポイント
大学の学部は数えきれないほど存在しています。自分にあった学部が見つからず、途方に暮れる方も多いでしょう。最低限のポイントを押さえるだけで学部選びをスムーズに行えます。引き続き大学の学部選びで押さえるべきポイントを解説します。
興味や関心のある分野を探る
学部を選ぶときは興味や関心のある分野を探るのが基本です。
たとえば、歴史に興味があるようであれば歴史学科のある文学部が候補となります。戦国時代の武将の名前を覚えるくらい日本史が好きであれば、特に日本史コースが適しているでしょう。
大学名のブランドを目当てに偏差値が高くない学部を狙って入学する方も少なくありませんが、関心の薄い分野だと入学してから勉強意欲を失いやすくなります。最悪のケースでは単位を取得できずに留年・中退する方もいます。
入学してからつらい思いをしないように、シンプルに好きなことを学べる学部を探してみましょう。
将来の職業や資格から逆算して考える
就職の観点から大学の学部を決めるときに重要なのが、将来の職業や資格から逆算して考えることです。
たとえば、医師になるためには医師国家試験、薬剤師になるには薬剤師国家試験を受験して合格しなければなりません。そのためには、国立あるいは私立の6年制大学の医学部、薬学部を受験する必要があります。
大学に入学してからなりたい職業を目指せないことに気づくと後悔してしまいます。専門職は特に資格の取得が求められる傾向です。漠然と専門職を目指したいという思いがある高校生は、早い段階でなりたい職業、必要な資格を明確にして学部を選びましょう。
医学部入試の詳細については下記のページでご確認ください。
対応している入試制度
大学受験では学部によって利用できる入試が異なることもあります。
たとえば、慶應義塾大学の文学部は一般選抜試験だけでなく、総合型選抜入試(自主応募制による推薦入学者選考)に対応しています。
選考方法は調査書・評価書・自己推薦書・総合考査 I・総合考査Ⅱとなっており、小論文や外国語による作文力、与えられたテーマについての記述などが評価されます。
相性の良い入試に対応した学部を選べば、大学受験を有利に進められるでしょう。
総合型選抜入試の概要や対策を詳しく知りたい方は下記の記事をご確認ください。
総合型選抜入試とは? 入試内容やスケジュール日程、一般選抜入試との違い、対策などを解説!
総合型選抜入試を制するためには書類審査と小論文の早期対策が必須!
学部に関するよくあるQ&A
ここまでの説明で学部について理解が深まったのではないでしょうか。さらに理解を深めるために学部に関するよくある質問についてQ&A形式で回答します。
Q1.学部と学科はどちらを先に選ぶべき?
A1.どちらが先でも問題ありません。
例として、漠然と理系に進みたいと考えている段階であれば、ひとまず理学部や工学部、理工学部、情報学部などをリサーチして、進路の視野を広げます。気になる学部が見つからなければ、文系の学部も探してみるとよいでしょう。
得意なことや強みがある方であれば学科から探すと効率的です。たとえば、AIと統計の両方が好きであれば、データサイエンス学科のようにどちらも学べる環境が見つかるでしょう。
Q2.学部が多い大学と少ない大学はどちらが良い?
A2.どちらが良いかは人によって異なります。
学部が多い大学は複数の異なる学問分野をまたがって研究が行われやすく、他学部の授業も履修しやすい環境です。興味の幅が広い人や極めたい学問が定まっていない人に適しています。
学部が少ない大学は高度な研究環境や人的なネットワークを形成している傾向です。特定の学問をとことん極めたい方、将来なりたい職業が決まっている方などにおすすめです。
Q3.就職に有利とされる学部はある?
A3.医療やビジネス、IT分野は比較的有利とされています。
ですが、就職に有利とされる学部に入学しても、本当に自分の学びたいことでなければ、知識やスキルの習得が中途半端になりやすいです。
採用担当者が重視する、知識やスキルを実社会で応用する力も採用試験でアピールできず、結果として就職活動に失敗するリスクが高まります。
就職に有利とされる学部を選ぶのではなく、自分が意欲的に楽しく学べる学部を選びましょう。
まとめ
大学の学部選びに失敗すると、社会人になってから興味のない職業に就くリスクが高くなります。やりたくない仕事を毎日するのはとてもつらいことです。
自分らしく輝いて働けるかどうかは、高校時代にどれだけ真剣に学部選びをしたかで決まります。ただ、社会経験のない高校生だと自分に適した学部を見つけるのが難しいのも事実です。必要に応じて進路に詳しいアドバイザーから助言を受けることをおすすめします。
目指す学部が決まらない方は、希望する学部の受験対策を相談したい方、弊社ホームページにて。